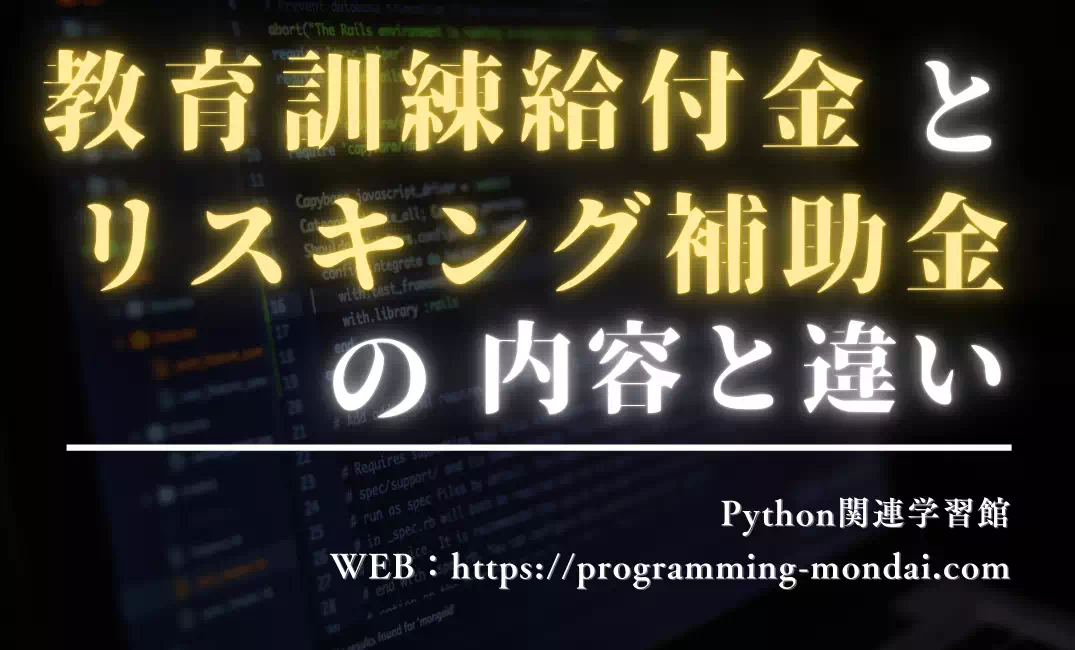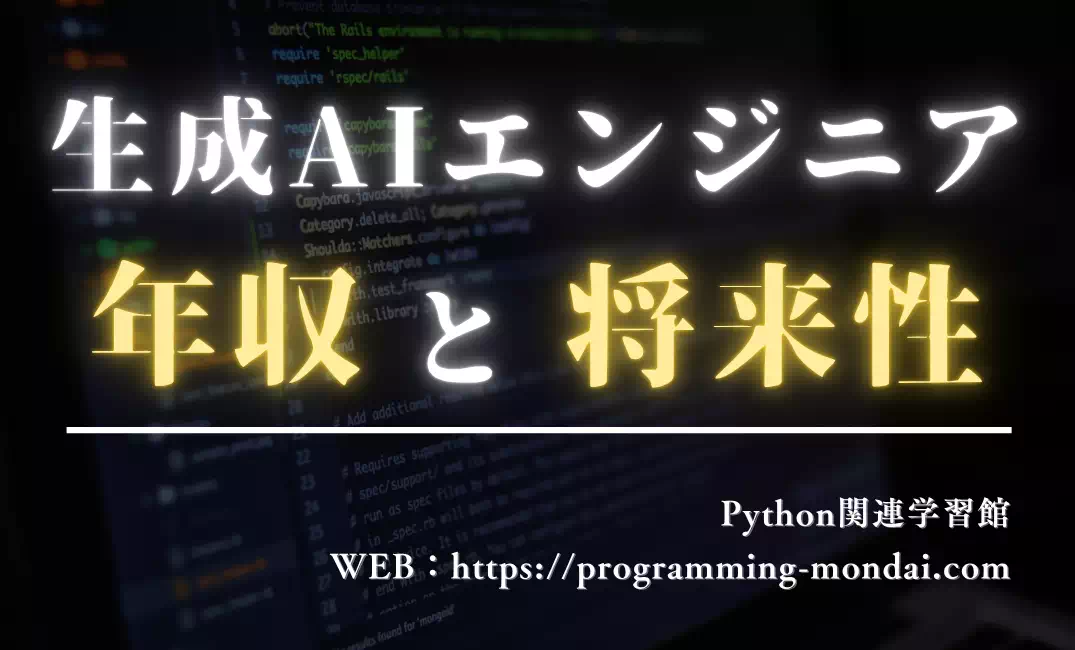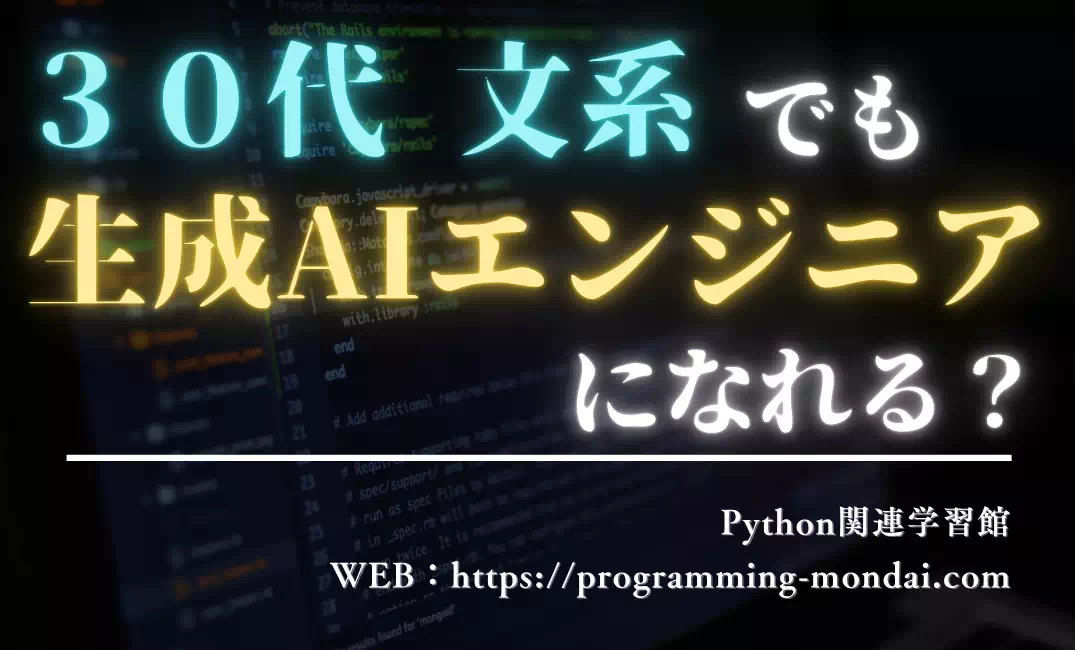【2026年版】生成AIスクール10社を徹底比較|学べる技術×目的でマッピング
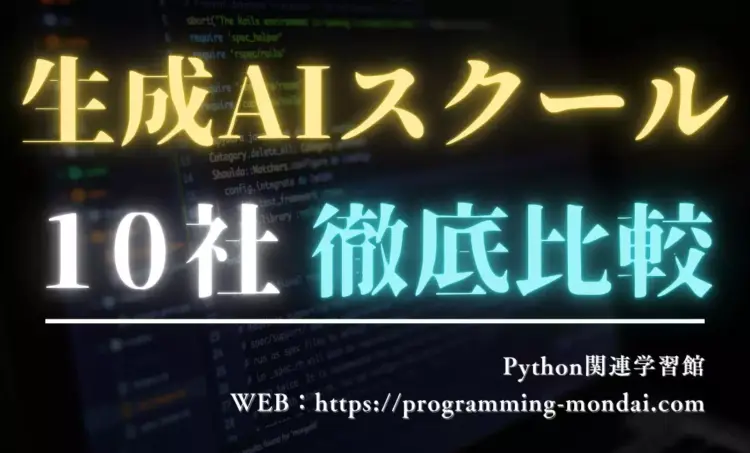
生成AIスクールが数が多くて「自分にはどこが合うのか分からない…」と感じていませんか。
料金もカリキュラムもサポートもそれぞれ違うので、公式サイトやおすすめ記事を見て回るほど、かえって迷ってしまう方も多いはずです。
とくに、
「転職したいのか、副業したいのか、まだはっきりしていない」
「Pythonも勉強したほうがいいのかな?」
という段階だと、どの生成AIスクールが自分に合っているのか判断するのが難しいですよね。
そこで本記事では、単なる「おすすめ◯選」ではなく、主要な生成AIスクール10社を
- 学べる技術領域(PythonでLLMアプリ開発/ノーコードで生成AI活用 など)
- 学ぶ目的(転職・副業・業務効率化・資格/リテラシー など)
という2つの軸で整理して、「自分に合うスクールの探し方」が分かるように解説していきます。
この記事は、Python入門やAI学習コンテンツを多数公開している「Python関連学習館」の視点から、「Pythonを書いて生成AIを本格的に扱いたい人」も、「ノーコードで業務に活かしたい人」も、どちらも迷わず選べるように構成しています。
まずは第1章で、このページの結論と「生成AIスクール比較マトリクス」の使い方をお伝えします。
ざっくり全体像をつかんでから読み進めてもらうと、後半の詳細比較もすっと頭に入りやすくなりますよ。
結論のマトリクス表を先に見たい方は こちら をクリックしてください。

補助金や助成金が使えて 受講料の70~80%がキャッシュバック
されるスクールもいくつかあるよ!
まず生成AIを学ぶ「目的」と「学び方」を整理しよう
いきなりスクールの名前を見比べるよりも先に、「自分はどんな目的で生成AIを学びたいのか」「どんな学び方が合っているのか」を整理しておくと、後の比較がぐっとラクになります。
ここでは、生成AIスクール選びの前提となる「目的」と「学び方」のパターンを、分かりやすく整理していきます。
結論のマトリクス表を先に見たい方は↓↓をクリックしてください。
生成AIスクールに通う目的を4つのタイプに分けてみる
生成AIスクールを選ぶうえで一番重要なのは、「どのスクールが有名か」ではなく、自分が何のために学ぶのかです。
目的が違えば、選ぶべきスクールも、学ぶべき内容もまったく変わります。
そこでまずは、生成AIスクールに通う目的を大きく4つのタイプに整理してみます。
この4タイプのどれに近いかを意識するだけで、「自分に合わない生成AIスクール」を避けられる確率は大きく上がります。
| タイプ | 主な目的 | こんな人に多い | 重視すべき学習内容 |
|---|---|---|---|
| 転職・キャリアチェンジ型 | AI・データ系職種への転職 | 未経験〜経験浅めのエンジニア / 異業種転職 | Python / LLMアプリ開発 / ポートフォリオ制作 |
| 副業・個人ビジネス型 | 収益化・案件獲得 | 会社員 / フリーランス | ノーコード / 業務自動化 / 実務ツール活用 |
| 業務効率化・社内DX型 | 今の仕事を楽にする | 企画職 / 管理職 / 現場リーダー | プロンプト設計 / 業務設計 / 再現性のある活用法 |
| 教養・リテラシー型 | 正しく理解する | 初心者 / 意思決定層 | 生成AIの基礎知識 / 活用事例 / リスク理解 |
どのタイプにも共通して言えるのは、「目的と学習内容がズレると失敗しやすい」ということです。
- 転職目的の場合
生成AIを「知っている」だけでは評価されません。
何を作れるのか、どう設計したのかを説明できることが重要なので、開発寄りのカリキュラムが必要です。 - 副業・個人ビジネス目的の場合
最初から難しい実装を学ぶより、「すぐ使える仕組み」を作れるかが大切です。
ノーコードやツール活用が中心のスクールのほうが成果につながりやすい傾向があります。 - 業務効率化・社内DX目的の場合
最新技術を追うより、「自分の業務にどう落とし込むか」が重要です。
実務に近い事例や、再現性のある考え方を学べるかを重視すべきです。 - 教養・リテラシー目的の場合
いきなりスキル習得を目指す必要はありません。
生成AIの仕組み、できること・できないこと、リスクを正しく理解できる内容が向いています。
Pythonでコードを書くか、ノーコードで学ぶかという選択
生成AIスクールを選ぶとき、多くの人が最初に悩むのが「Pythonなどのコードを書くべきか、それともノーコードで学ぶべきか」という点です。
ここを感覚で選んでしまうと、「思っていた学習内容と違った」「途中で挫折した」というミスマッチが起きやすくなります。
まずは、それぞれの学習スタイルの違いを整理してみましょう。
| 学習スタイル | 特徴 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Pythonでコードを書く | 自由度が高く本格的 | 転職志向 / 技術を深く学びたい人 | 学習負荷が高く挫折しやすい |
| ノーコード中心 | 初心者OK・成果が早い | 副業 / 業務効率化目的 | 技術理解は浅くなりがち |
Python学習が向いているケース
Pythonを使った学習は、主に以下のような目的に向いています。
- AI・データ系職種への転職を目指している
- 生成AIを使ったアプリやツールを自分で作りたい
- 将来的に技術的な選択肢を広く持っておきたい
Pythonを学ぶ最大のメリットは、「できることの幅が広がる」ことです。
一方で、プログラミング未経験の場合は、環境構築やエラー対応でつまずきやすく、
「生成AI以前のところで挫折する」ケースも少なくありません。
ノーコード学習が向いているケース
ノーコード中心の学習は、以下のような人に向いています。
- すぐに業務や副業で使いたい
- 技術そのものより成果を重視したい
- プログラミングに強い苦手意識がある
ノーコードの強みは、短期間で「使える状態」になりやすいことです。
特に業務効率化や副業目的の場合、コードを書くこと自体は必須ではありません。
ただし仕組みの理解が浅いままだと、応用が効かず、ツール依存になりやすい点には注意が必要です。
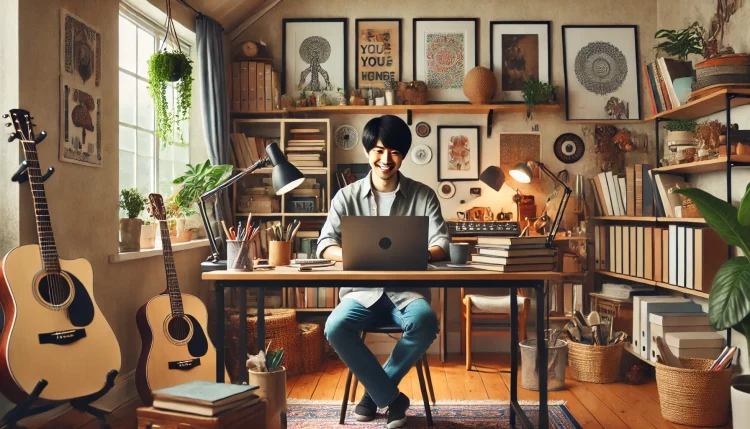
学べる技術領域 × 目的で見る生成AIスクールマトリクス
ここからは10社の生成AIスクールを、「学べる技術領域」と「受講目的」という2つの軸で並べて見ていきます。
それぞれのスクールがどの分野に強いのか、どんな目的の人と相性が良いのかを一度に眺められるようにすることで、あなたに合う候補をぐっと絞り込みやすくなります。
10社マトリクス一覧表で見る、それぞれの得意分野
ここからがこの章のメインです。
10社の生成AIスクールを「学べる技術領域」と「受講目的」で整理したマトリクスを、表のかたちでまとめました。
この表では、全体の傾向がパッと分かるように、次の記号を使っています。
- ◎:特に強い/そのスクールのメイン領域
- ○:しっかり学べる
- △:メインではないが学べる
- -:基本的にはあまり扱わない
それでは実際のマトリクスを見ていきましょう。
| スクール名 | Python+ 生成AI ※1 | ノーコード+ 生成AI ※2 | データサイエンス寄りAI ※3 | プロンプト・生成AIリテラシー ※4 | 転職・キャリアチェンジ | 副業・個人ビジネス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMM 生成AI CAMP 生成AIエンジニアコース | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| DMM 生成AI CAMP Difyマスターコース | △ | ◎ | - | ○ | ○ | ◎ |
| Aidemy | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| キカガク | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | |
| データミックス | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 侍エンジニア | ○ | △ | △ | △ | ◎ | △ |
| TechAcademy | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| AVILEN | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| スキルアップAI | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ |
| SHIFT AI | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ |
| 僕のAIアカデミー | △ | ◎ | - | ○ | △ | ◎ |
この表を、「生成AIスクールの地図」として眺めてみてください。
例えば、次のような読み方ができます。
- Pythonを書いてLLMアプリ開発までやりたい人は、DMM/Aidemy/データミックス/キカガク/侍エンジニアあたりが候補になりやすいです。
- ノーコード中心で副業や個人ビジネスに活かしたい人は、僕のAIアカデミーやSHIFT AIが強めです。
- 現職の業務効率化・社内DXを進めたい人は、AVILEN/スキルアップAI/SHIFT AI/キカガクあたりに注目すると、自分に合うスクールを見つけやすくなります。
もちろん、1つのスクールが複数の領域・目的をカバーしていることも多いので、「自分はここ!」と1マスに決めつける必要はありません。
ただ、
- 技術領域の軸で「Python寄りか、ノーコード寄りか」
- 受講目的の軸で「転職寄りか、副業寄りか、業務効率化寄りか、資格寄りか」
この2本の軸を意識するだけでも、選びやすさはかなり変わってきます。
技術領域は大きく4つに分けて考える
「このスクールでは何が学べるのか?」という技術領域を、ざっくり4つに分けて紹介しました。
スクールによっては複数の領域をカバーしているので、「どこに特に強みがあるか」という感覚で見てもらえれば大丈夫です。
Python+LLMアプリ開発の領域
ChatGPT API や各種LLM、RAG、エージェントなどを扱いながら、Pythonコードを書いて生成AIアプリを開発するタイプの学び方です。
ここが強いスクールは、生成AIエンジニアやAIエンジニア寄りのキャリアを目指す人との相性が良くなります。
ノーコード+生成AIツール活用の領域
ChatGPTやClaude、画像・動画生成ツール、ノーコード自動化ツールなどを組み合わせて、業務効率化やコンテンツ制作、副業ビジネスなどに役立てるスタイルです。
コードを書くよりも、「どう使えば成果が出るか」を重視する人に合っています。
データサイエンス寄りAIの領域
統計・機械学習・データ分析などの土台を押さえつつ、その上に生成AIをどう組み込むかを考えるタイプの学び方です。
データサイエンティストやデータ分析人材としてのキャリアを意識している人にとって重要な領域になります。
プロンプト・生成AIリテラシーの領域
「生成AIとは何か」「ビジネスでどう活用するか」「どんなリスクや注意点があるか」といったリテラシー面や、プロンプトの書き方・業務フローへの組み込み方にフォーカスした学び方です。
エンジニアに限らず、ビジネス職や教育現場にも広く関わってくる部分ですね。
あなた自身が、「この4つのうち、どこを重点的に伸ばしたいか?」を意識しておくと、後でマトリクスを見たときに「このスクールとは相性が良さそうだな」と判断しやすくなります。

生成AIスクール10社の特徴とざっくり比較
ここからは、この記事で扱う生成AIスクール10社の特徴を、ざっくりと押さえていきます。
「このスクールはどんな雰囲気なのか」「どんな人と相性が良さそうか」を先にイメージしておくと、後でマトリクス表を見るときにも理解しやすくなります。
ここでは細かい料金やカリキュラムの全てを説明するのではなく、“このスクールはどのポジション寄りなのか” が伝わるようにまとめていきます。
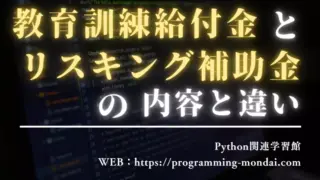
DMM 生成AI CAMP【生成AIエンジニアコース】の価格と特徴

当サイトの一押し!
補助金はなくてもDMM独自のキャッシュバックキャンペーンにより、圧倒的なコスパを実現するよ!
| 受講料目安 | 296,000円~ | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | 期間プラン型 | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
DMM 生成AI CAMP は、その名のとおり生成AIに特化したオンラインスクールで、プロンプトエンジニアリングの基礎から、生成AIアプリ開発までカバーしているのが大きな特徴です。
ChatGPT などのツール活用だけでなく、PythonやAPI連携、RAG(検索と組み合わせたLLM)といった、開発寄りの内容まで一気通貫で学べる構成になっています。
「生成AIを“使う人”で終わらず、“作る側”にも回ってみたい」「将来的に生成AIエンジニア寄りの仕事も視野に入れておきたい」と考えている方に、特にマッチしやすいスクールです。
Python をしっかり書くことになりますが、その分、エンジニア転職や高度な業務自動化につながるスキルを身につけやすいポジションと言えるでしょう。
DMM 生成AI CAMP 【生成AIエンジニアコース】については、詳細なレビュー記事もありますので、是非↓↓のリンクから移動して確認して下さい。

DMM 生成AI CAMP【Difyマスターコース】の価格と特徴

当サイトの一押し!
補助金はなくてもDMM独自のキャッシュバックキャンペーンにより、圧倒的なコスパを実現するよ!
| 受講料目安 | 278,000円~ | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | 期間プラン型 | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
DMM 生成AI CAMP の Difyマスターコースは、「生成AI×業務自動化」に振り切ったコースで、プログラミング知識ゼロでも、 “ノーコード〜ローコード” で生成AIアプリを作れる状態を目指します。
Pythonでガッツリ開発するというよりは、「現場の業務フローに合わせて、AIアプリを素早く構築して回す」方向に強いので、営業・マーケ・企画・バックオフィスなどのビジネス職でも、成果に直結しやすいポジションにあります。
また、Difyによるアプリ開発に精通したメンターが伴走し、無制限のチャットで質問できるなど、独学で詰まりやすいポイントを潰しながら進めやすい設計になっています。
「社内の手作業を自動化したい」「部署内で使えるAIチャットボットや検索アプリを作りたい」といった実務目的はもちろん、キャリアアップ/副業収入アップを狙って“ノーコード開発での生成AI活用”を武器にしたい人にも検討しやすいコースです。
DMM 生成AI CAMP 【Difyマスターコース】については、詳細なレビュー記事もありますので、是非↓↓のリンクから移動して確認して下さい。
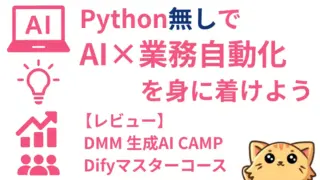
Aidemy(アイデミー)の価格と特徴
| 受講料目安 | 327,800円~ | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | 期間プラン型 | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象 | キャリア支援 | あり |
Aidemy は、もともと「Python で学ぶAI・データサイエンス」のオンラインスクールとして知られており、近年は生成AI活用の講座も充実してきています。
ChatGPT のプロンプトエンジニアリングや GPTs(MyGPT)、Dify を使ったLLMアプリ開発までを扱う実践講座も提供しており、「Python×生成AI×業務効率化」という組み合わせを学びやすい環境です。
Python の基礎からAI・機械学習、そして生成AI活用まで、一歩ずつステップアップしていける講座構成が多いので、「今はほぼ初心者だけど、最終的には仕事で使えるレベルまで行きたい」という社会人にも向いています。
質問がしやすいサポート体制が整っている点も、独学で挫折しがちな方には安心材料になるでしょう。
転職・キャリアチェンジを視野に入れつつも、「まずは現職での業務効率化から始めたい」という方にとって、バランスの良い選択肢になるタイプのスクールです。
キカガク(Kikagaku)の価格と特徴
| 受講料目安 | 792,000円~ | 無料体験 | あり |
| 料金形態 | 買い切り | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
キカガクは、DX人材育成やAI研修の分野でよく名前が挙がるスクールで、企業向け研修の実績も豊富です。
生成AIに関しては、ビジネスでの活用や業務効率化にフォーカスした入門コースや、実務に組み込むことを目指した「生成AIビジネス実践」のようなコースを提供しています。
どちらかというと、純粋なエンジニア転職というより、「ビジネスサイドでAI・生成AIを活用できる人材を増やす」という方向性が強いスクールです。
DX推進担当者や、社内で生成AIの使い方を啓蒙する立場を目指している人にとって、実務に近い知識やワークフローを学びやすいポジションにあります。
また、教育訓練給付制度に対応した講座も多く、長期的にAIスキルを磨いていきたい社会人にとって、費用面のハードルを下げやすい点も特徴です。
データミックス(DataMix)の価格と特徴
| 受講料目安 | 940,500円~ | 無料体験 | あり |
| 料金形態 | 買い切り | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
データミックスは、「データサイエンティスト養成」や「データ分析人材育成」で知られているスクールで、近年は生成AI・機械学習エンジニア寄りの講座も展開しています。
データ分析・統計・機械学習の地盤があり、その上に生成AIをどう組み合わせるか、といった視点で学べるのが特徴です。
Python を使ったデータ前処理やモデル構築、可視化といった基本を押さえたうえで、「生成AIをどう業務やサービスに組み込むか」を考えたい人には、相性のよいスクールと言えます。
単にツールとして生成AIを使うのではなく、データ活用全体の流れの中で位置づけたい方に向いています。
転職・キャリアチェンジ型の中でも、「データサイエンス寄りのキャリア」を目指す場合は、他のスクールと比べるうえで重要な候補になってくるでしょう。
また、教育訓練給付制度に対応した講座も多く、長期的にAIスキルを磨いていきたい社会人にとって、費用面のハードルを下げやすい点も特徴です。
侍エンジニア(生成AI/AIコース)の価格と特徴
| 受講料目安 | 198,000円~ | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | 買い切り | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象 | キャリア支援 | あり |
侍エンジニアは、マンツーマン指導型のオンラインプログラミングスクールとして有名で、近年はAIや生成AI関連のコースも展開しています。
専属の講師と1対1で学習を進められるスタイルなので、「自分のペースや目標に合わせてカリキュラムを組みたい」という方に向いています。
Python を使ったプログラミング学習と組み合わせやすい点もあり、「未経験からエンジニア転職を目指しつつ、生成AIも扱えるようになりたい」といったニーズとは相性が良いスクールです。
マンツーマンゆえに料金はやや高めになりがちですが、その分きめ細かいサポートを重視したい人に選ばれています。
自己管理が苦手で、「誰かに伴走してもらわないとサボってしまいそう」という方は、候補に入れておく価値があるでしょう。
TechAcademy(テックアカデミー)の価格と特徴
| 受講料目安 | 149,600円~ | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | 買い切り | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | なし |
TechAcademy は、大手オンラインプログラミングスクールの一つで、Web開発やPython、デザインなど多様なコースを提供しています。
その中で生成AI関連としては、「はじめてのプロンプトエンジニアリング」など、生成AI時代を意識した入門コースが用意されています。
特徴としては、完全オンライン+メンターサポートありという従来のTechAcademyスタイルで、「プログラミングやITの学習経験がほとんどない人でも、比較的入りやすい構成」になっていることです。
まずはプロンプトエンジニアリングや、生成AIツールの基本的な使い方から押さえたい方には、入り口としてちょうど良い難易度と言えます。
すでにPythonやWeb開発をTechAcademyで学んだことがある方なら、同じ環境で生成AI入門コースを受けてみる、という流れも取りやすいはずです。
AVILEN(アヴィレン)の価格と特徴
| 受講料目安 | 22,000円/人~ | 無料体験 | あり |
| 料金形態 | 買い切り | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
AVILEN は、G検定・E資格といったAI資格の対策講座や、企業向けのAI研修で広く知られているスクールです。
生成AIについても、ビジネス活用やプロンプトエンジニアリング、社内研修向けコンテンツなどを多数提供しており、「AIリテラシー+生成AI活用」をまとめて学びやすいポジションにあります。
特徴的なのは、「AIを業務やビジネスにどう落とし込むか」という観点が強いことです。
エンジニアだけでなく、ビジネスサイドの社員向け研修も多いため、「社内でAI活用を広げる役割を担いたい」「資格を取りつつ、生成AIの活用方法も押さえておきたい」といったニーズに応えやすいスクールだと言えます。
資格学習と組み合わせて学びたい方や、組織全体でAIリテラシーを上げていきたい方には、特に検討しやすい選択肢でしょう。
スキルアップAIの価格と特徴
| 受講料目安 | 27,500円/人~ | 無料体験 | あり |
| 料金形態 | 買い切り | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
スキルアップAIは、AI・機械学習・データサイエンス・DXといった領域の研修を幅広く提供しているスクールです。
生成AIに関しても、業務効率化やビジネス活用に焦点を当てた講座や、エンジニア向け・ビジネス向けそれぞれの入門〜応用コースが用意されています。
企業研修の実績が多いこともあり、「現職での業務改善」「社内DX」「部署単位でのスキル底上げ」といったニーズに向いているスクールです。
一方で、個人向けコースもオンラインで提供されているので、「仕事で必要になってきたから生成AIをちゃんと学びたい」という社会人にもマッチしやすいでしょう。
「幅広くAIを学びたいが、その中でも生成AIの活用を押さえておきたい」という方は、カリキュラム構成をチェックしながら候補に入れておくと良いと思います。
SHIFT AIの価格と特徴
| 受講料目安 | 月額 21,780円 | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | サブスク | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | なし |
SHIFT AI は、「AIが好きな人のコミュニティ」をコンセプトにしたオンラインの学習コミュニティ・スクールです。
生成AIに関する動画講座や勉強会、イベント配信などがセットになっていて、情報感度の高いメンバーと一緒にアップデートを追いかけられるのが特徴です。
純粋な「カリキュラム型スクール」というより、「コミュニティ+講座」という形なので、「一人で黙々と勉強するより、仲間がいる環境で続けたい」というタイプの人に向いています。
副業や個人ビジネス、社内DXなど、参加者の目的もさまざまなので、いろいろな事例に触れられる点も魅力です。
「生成AIを使いこなす仲間がほしい」「流行の変化が早すぎて、一人だとついていけるか不安」という方は、他のスクールと併用する形も含めて検討しやすいポジションです。
僕のAIアカデミーの価格と特徴
| 受講料目安 | 228,000円〜 | 無料体験 | なし |
| 料金形態 | 一括+サブスク | オンライン完結 | 〇 |
| 教育訓練給付金 | 対象外 | 質疑 / 添削 | あり |
| リスキリング補助金 | 対象外 | キャリア支援 | あり |
僕のAIアカデミーは、「AIを活用して自分で収入を得る力を身につける」というコンセプトの生成AIスクールです。
ChatGPT や画像・動画生成AI、ノーコードツールなどを組み合わせて、副業・個人ビジネスに直結するスキルを短期間で学べるカリキュラムが用意されています。
特徴としては、エンジニア転職というよりも、「今の仕事に+αで収入源を作りたい」「自分の商品やサービスを作ってみたい」といった人向けの内容が多い点です。
たとえば、デジタルコンテンツの制作・販売や、AIツールを使った業務代行、SNSやブログ運営など、現実的なビジネスの題材を扱うケースが目立ちます。
Python をガッツリ書くというよりは、ノーコードや生成AIツールをうまく組み合わせてアウトプットを作っていくスタイルなので、「コードが苦手だけど、副業にチャレンジしてみたい」という方には特に検討しやすいスクールです。
僕のAIアカデミー については、詳細なレビュー記事もありますので、是非↓↓のリンクから移動して確認して下さい。

タイプ別|自分に合う生成AIスクールの絞り込み方
ここからは、第4章のマトリクスをもとに、「自分はどのタイプに近いのか?」という視点から、具体的にスクール候補を絞り込んでいきます。
完璧に1つのタイプに当てはまる必要はありませんが、「一番近いタイプ」と「次に近いタイプ」を意識して読むと、かなり選びやすくなるはずです。
Pythonを書いてLLMアプリ開発までやりたい人向け
まずは、「Pythonを書いて、LLMアプリや生成AIエンジニア寄りのスキルを身につけたい」というタイプから見ていきましょう。
このタイプの方は、将来的にエンジニア転職や高度な自動化ツールの開発などを視野に入れているケースが多いです。
この場合、候補になりやすいのは次のようなスクールです。
- DMM 生成AI CAMP
- Aidemy(アイデミー)
- データミックス(DataMix)
- キカガク(Kikagaku)
- 侍エンジニア
これらのスクールは共通して、「Python+LLMアプリ開発」の領域に強みがあります。
一方で、それぞれ少しずつカラーが違うので、次のポイントで比べてみると判断しやすくなります。
- DMM 生成AI CAMP:
生成AIエンジニア寄りの内容が濃く、RAGやAIエージェントなど、最新のトピックまでカバーしているのが強みです。「とにかく生成AIど真ん中でやっていきたい」という人は、まず候補に入れておきたいスクールです。 - Aidemy:
Pythonの基礎からAI・機械学習、生成AIとステップアップしやすく、オンライン完結で質問サポートも手厚いのが特徴です。「今はほぼ未経験だけど、中長期的にAIエンジニア寄りのスキルをつけたい」という社会人に向いています。 - データミックス:
データサイエンス寄りの土台がしっかりしていて、「データ分析 × 生成AI」の文脈で学びたい人に合うスクールです。将来的にデータサイエンティストやデータエンジニア寄りのキャリアを狙うなら、候補としてチェックしておきたいところです。 - キカガク:
エンジニア専業というより、「DX人材としてAI・生成AIを扱えるようになりたい」層に向いた構成が多めです。Pythonも使いつつ、ビジネス側の視点を持っていたい場合は、他の候補と比べてみるとバランス感がつかみやすいでしょう。 - 侍エンジニア:
マンツーマンで自分専用カリキュラムを組みたい人向けです。「独学では続かない」「自分に合わせてカリキュラムを調整してほしい」という場合、費用はそれなりにかかりますが、学習効率や継続しやすさの面でメリットがあります。
PythonでLLMアプリ開発を目指す場合は、
- どのくらい本気でエンジニア転職をしたいか
- データサイエンス寄りか、アプリ開発寄りか
- どの程度、手厚いサポート(メンター・質問対応)を重視するか
といった点を軸に、2〜3社まで候補を絞り込んでみると良いと思います。
ノーコード中心で副業・個人ビジネスをしたい人向け
次は、「コードは最小限にして、ノーコード+生成AIで副業や個人ビジネスに挑戦したい」というタイプです。
本業を続けながら、コンテンツ制作や業務代行、デジタル商品販売など、比較的始めやすい形で収入源を増やしたい人がここに当てはまります。
このタイプの方にとって、有力な候補になるのは次のようなスクールです。
- 僕のAIアカデミー
- SHIFT AI
- 僕のAIアカデミー:
「生成AIを使って自分で稼ぐ」ことにかなりフォーカスしたスクールです。ノーコードツールやAIを使ったコンテンツ制作、商品設計の考え方など、「どうやってビジネスに落とし込むか」という視点が強いのが特徴です。
「とにかく小さくてもいいから売上を作ってみたい」という人には、かなり相性が良いはずです。 - SHIFT AI:
は、コミュニティ型でさまざまな事例やノウハウに触れられる環境が魅力です。副業・起業の話題も多く、「自分と似たレベルや志向の人たちがどんなことをしているのか」を知れるのが大きなメリットです。
1つのスクールで完結させるというより、他のツールや学習と併用して「情報と仲間を得る場」として使うイメージに近いかもしれません。
ノーコード×副業タイプの方は、
- どの程度、すでに持っている「強み」や「テーマ」があるか
- ひとりでビジネス構想を練るのが得意か、それともコミュニティの力を借りたいか
- どこまで“稼ぎ”にコミットしたいか(お小遣いレベルか、本気の副業か)
といったポイントで、スクールの雰囲気との相性を見ていくと、ミスマッチを防ぎやすくなります。
現職の業務効率化・社内DXを進めたい人向け
続いて、「今の会社の仕事を続けながら、生成AIで業務を効率化したい」「社内のDX推進役として動きたい」というタイプです。
このタイプは、必ずしもエンジニア転職を目指しているわけではなく、「自分の部署やチームで成果を出すこと」が第一の目的になっていることが多いです。
この目的にハマりやすいスクールとしては、次のようなところが挙げられます。
- AVILEN
- スキルアップAI
- キカガク
- SHIFT AI
- AVILEN とスキルアップAI:
企業向けの研修実績が豊富で、「ビジネス職向けの生成AI活用講座」や「社内向けのAIリテラシー研修」に強みがあります。
個人でも受講できるコースを通じて、業務に直結する生成AIの活用法や、社内に広めるためのポイントを学びやすいのが特徴です。 - キカガク:
DX人材育成の文脈でのコースが多く、「自社の業務フローにAIをどう組み込むか」を考えるのに役立つ内容がたくさんあります。
教育訓練給付対象の講座を利用すれば、自己負担を抑えながら、比較的長期の学習計画を立てることも可能です。 - SHIFT AI:
「業務効率化に成功した人の事例」や「会社での導入の進め方」をコミュニティ経由で知ることができる点が魅力です。
スクール単体だけでは分からない、現場目線のノウハウに触れられるのは、社内DX型の人にとってプラスになりやすい部分です。
業務効率化・社内DXを目的にする場合は、
- 自分の業務内容(事務・営業・マーケ・企画など)に近い事例を提示してくれるか
- 社内説得や上申のために使える「資料・根拠」が学べそうか
- 個人受講だけでなく、将来的に部署やチームにも広げやすいか
といった視点でスクールを見ていくと、「現場で役立つかどうか」の判断がしやすくなります。
資格・教育・リテラシー重視の人向け
最後に、G検定やE資格などの資格取得や、学校・会社で「人にAIを教える側」に立ちたい人向けのパターンを見ていきます。
このタイプは、「すぐに転職したい」というより、「中長期的にAIリテラシー全体を底上げしたい」というニーズが中心になることが多いです。
この目的に合いやすいスクールは、次のようなところです。
- AVILEN
- スキルアップAI
- キカガク
- AVILEN:
G検定・E資格対策講座でよく知られており、AI全般の基礎から応用まで体系的に学べる環境があります。
これに加えて、生成AIリテラシーやビジネス活用のコースも用意されているため、「資格+生成AI」を一体として学びたい方には心強い選択肢です。 - スキルアップAI:
資格対策+ビジネス活用に強く、企業研修などを通して「教える側」としての視点を身につけられる場面が多くあります。
将来的に社内講師や研修担当としてAI・生成AIを教えたい人にとって、参考になるポイントが多いはずです。 - キカガク:
教育訓練給付対応の長期講座などを通して、AI・データサイエンス・生成AIをまとめて学べる構成が多いです。
「まずは自分のリテラシーを底上げして、その後に教育や社内展開にも活かしたい」という場合には、じっくり取り組みやすいスクールと言えるでしょう。
資格・教育・リテラシー重視の方は、
- 自分がどの資格に興味があるか(G検定、E資格など)
- 資格取得そのものが目的なのか、その先に何をしたいのか(教員・研修担当・社内布教など)
- 生成AIの具体的な活用スキルと、どの程度セットで学べるか
を整理したうえで、3社程度を比較してみると、自分に合うスクールが見つかりやすくなります。
迷ったときの決め方:候補を2〜3社に絞って比較する
ここまで読んでみて、「どのタイプも少しずつ当てはまる気がする…」と感じている方もいるかもしれません。
その場合は、次のようなステップで考えると、具体的な比較に落とし込みやすくなります。
1.「今いちばん強い目的はどれか」を1つだけ選ぶ。
2.「Pythonを書くかどうか」を決める。
3.残ったスクールの中から、2〜3社に絞り込むことです。
一発で「ここしかない!」と決める必要はありません。
まずはこの記事のマトリクスやタイプ別の解説を使って、「自分に合いそうな候補を2〜3社まで減らす」ことができれば、スクール選びの半分くらいは終わったも同然です。
次の章では、どのスクールを選ぶ場合にも共通して役立つ「生成AIスクール選びで失敗しないためのチェックリスト」をまとめていきます。
ここまでで候補が何校か見えてきた方は、そのスクールを思い浮かべながら読み進めてみてください。

生成AIスクール選びで失敗しないためのチェックリスト
ここまでで、「自分の目的」と「学び方」、そして「候補になりそうなスクール」がだいぶ見えてきたと思います。
この章では、いよいよ申し込みを検討する段階で、「あとから後悔しないために必ずチェックしておきたいポイント」を整理していきます。
スクールの公式サイトは基本的に良いことしか書いていないので、ここで挙げるチェック項目を手元に置きながら、落ち着いて1つずつ確認していくのがおすすめです。
カリキュラムで必ず確認したいポイント
まずは、もっとも重要なカリキュラムの確認ポイントから見ていきます。
「何を学ぶか」が自分の目的とズレていると、どれだけサポートが手厚くても満足度は上がりにくいので、ここは丁寧にチェックしておきましょう。
一つ目のポイントは、自分の目的とカリキュラムがきちんと対応しているかどうかです。
たとえば、
- 転職・キャリアチェンジが目的なのに、ビジネスリテラシー寄りの内容が多すぎないか
- 副業・個人ビジネスが目的なのに、研究寄り・理論寄りの内容ばかりになっていないか
- 業務効率化が目的なのに、自分の業務とは縁遠い題材ばかりではないか
といった点は、カリキュラムや受講事例・卒業生インタビューなどから、ある程度読み取ることができます。
二つ目のポイントは、「コードを書くかどうか」の比重です。
Python をしっかり書くスクールなのか、ノーコード+プロンプトが中心なのかは、公式サイトのカリキュラム説明にかなりはっきり出ます。
- PythonやAPI、RAG、エージェント開発などのキーワードが多く出てくる → コード寄り
- ChatGPTや画像生成、ノーコード自動化ツール、ワークフロー構築などが中心 → ノーコード寄り
あなた自身が「どちらの学び方を選ぶか」は第2章で整理しましたが、ここで改めて「実際のカリキュラムと一致しているか」を確認しておくと安心です。
三つ目のポイントは、「具体的にどんなアウトプットが作れるのか」です。
最終的に作るもの(ポートフォリオ・ビジネスアイデア・業務改善提案など)が明示されているスクールのほうが、ゴールがイメージしやすく、モチベーションも保ちやすくなります。
- 転職向けなら:ポートフォリオになるアプリや分析レポートが作れるか
- 副業向けなら:販売可能なコンテンツやサービスの形まで落とし込めるか
- 業務効率化向けなら:自分の業務に近い自動化フローやテンプレートがあるか
といった観点で、「学びの最後に何が手元に残るか」をチェックしてみてください。
学習サポート・コミュニティで確認したいポイント
次に、学習サポートとコミュニティについてのチェックポイントです。
内容が良くても、「分からないところを聞けない」「一人で黙々とやるだけで続かない」となると、途中で挫折しやすくなってしまいます。
一つ目のポイントは、質問のしやすさです。
スクールによって、
- チャットでいつでも質問できる
- 週に◯回までメンタリング・面談がある
- 質問対応はフォーラム形式のみ
など、仕組みはかなり差があります。
あなたの性格や生活スタイルに合わせて、「自分が実際に活用できそうか」をイメージしてみましょう。
二つ目のポイントは、コミュニティや受講生同士の交流有無です。
オンラインスクールはどうしても孤独になりやすいので、
- 受講生限定のDiscordやSlackがあるか
- 勉強会やイベント、もくもく会などが実施されているか
- 質問や成果物をシェアし合える場があるか
といった点は、継続のしやすさに直結します。
特に、SHIFT AI のようなコミュニティ色の強いサービスと併用する場合は、「自分がどの場をメインにするか」も意識しておくと良いですね。
三つ目のポイントは、学習ペースの支援やスケジュール管理です。
社会人にとって、「どう時間を捻出するか」は非常に大きな課題です。
- 週に何時間くらいの学習を想定しているか
- スケジュール表や進捗管理ツールが提供されているか
- サボっていると声をかけてくれる仕組みがあるか
こうした点を事前に確認しておくと、「仕事が忙しくなった瞬間にフェードアウトしてしまう」というリスクをかなり減らせます。
料金・期間・給付金・返金制度でチェックすべきこと
最後に、料金や期間、給付金・返金制度などのお金まわりの話です。
ここはどうしても現実的な部分になりますが、「高い=悪い」「安い=良い」とはいかないので、落ち着いて要素を分解して見ていきましょう。
総額と期間のバランス
たとえば、
- 3か月で◯◯万円
- 6か月で◯◯万円
- 月額制で受け放題
など、料金体系はスクールによってさまざまです。
重要なのは、「その期間内に、自分がどこまでコミットできそうか」です。
- 週にどれくらい時間が取れそうか
- 期間中に忙しくなりそうなイベント(繁忙期・引っ越し・家族の都合など)がないか
- 無理をしすぎずに、だいたいのカリキュラムを終えられそうか
といった点を、冷静に自己評価してみてください。
教育訓練給付金や補助金の対象か
DMM 生成AI CAMP などのいくつかのスクールでは、厚生労働省の教育訓練給付金の対象講座になっているケースがあります。
対象条件に当てはまるなら、実質負担を大きく下げられる可能性があるので、見逃すのはもったいない部分です。
また、自治体や会社独自の補助制度が使える場合もあるので、気になるスクールがある程度絞れたら、「給付金」「補助金」「会社の教育制度」なども一度チェックしてみると良いでしょう。
返金保証や途中解約の条件
スクールによっては、
- 一定期間内なら全額返金保証あり
- 初回カリキュラム受講後までなら部分返金あり
- 途中解約は不可、または条件付き
など、制度がかなり異なります。
返金制度があれば必ず使う、という話ではありませんが、「もし完全にミスマッチだった場合の保険」として、事前にルールを把握しておくことは大切です。
とくに、高額なコースを検討している場合は、
- 無料相談やカウンセリングで不安を解消できるか
- 初回の面談で「これは違う」と感じた場合にどう対応してくれるか
なども含めて、納得したうえで申し込むようにすると、心理的な負担も軽くなります。
ここまでが、「生成AIスクール選びで失敗しないためのチェックリスト」です。
この章の内容をもとに、自分が気になっている2〜3社について、一度じっくりと公式サイトを見比べてみると、「ここなら頑張れそうだな」と感じるスクールが少しずつ見えてくるはずです。
次の章では、実際によくある疑問をQ&A形式でまとめていきます。
「そもそもスクールに通うべきか」「Pythonは必須なのか」など、迷いやすいポイントを整理しますので、最終的な判断の前に、ぜひ一度目を通してみてください。
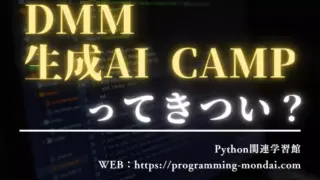
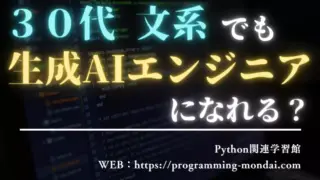
よくある質問(FAQ)
最後に、生成AIスクール選びでよくいただく質問を、Q&A形式でまとめておきます。
ここまでの内容を読んで「まだモヤっとしているところ」があれば、この章で一度整理してみてください。
生成AIスクールに通うべきか、独学だけでも十分ですか?
この質問はとても多いです。
結論から言うと、「どこまで目指すか」と「自分の性格」によって最適解は変わります。
まず、独学だけでも十分なケースとしては、次のようなイメージがあります。
- まずは生成AIツールの基礎的な使い方を知りたい
- 簡単な業務効率化(メール文作成、文章の要約、アイデア出し)から試したい
- 無料〜低価格の書籍やオンライン記事で、コツコツ勉強するのが苦にならない
このくらいのレベルであれば、独学+実務での試行錯誤でも十分に力をつけていくことができます。
一方で、スクールを利用したほうが効率的なケースはこんな場合です。
- エンジニア転職や、生成AIエンジニア寄りのキャリアチェンジを本気で目指したい
- 副業や個人ビジネスで「実際に売上を立てるところ」まで伴走してほしい
- 現職のDX推進など、会社からも期待されていて、短期間でキャッチアップする必要がある
- 一人だとどうしても学習ペースが崩れがちで、体系的に学ぶのが苦手
スクールは、「体系立てて学べること」「分からないときに相談できること」「一定期間コミットしやすい環境を作ってくれること」が強みです。
目標や期限がある場合には、上手に活用すると遠回りを減らせます。
迷ったときは、
- まずは独学で1〜2か月ほど試してみる
- その上で、「独学の限界」を感じたタイミングでスクールを検討する
という2段階方式もおすすめです。
生成AIを仕事で活かすには、Pythonは必須ですか?
Pythonを学ぶべきかどうかも、よく悩まれるポイントです。
結論としては、「必須ではないが、目指すレベルによって重要度が変わる」と考えておくと分かりやすいです。
Pythonが必須ではないケースは、次のようなイメージです。
- 業務の中で、文章・資料作成やアイデア出しに生成AIを使うのが中心
- 画像・動画生成ツールを使って、デザインやコンテンツ制作の効率を上げたい
- ノーコードツールを組み合わせて、簡単な自動化やチャットボットを作りたい
このレベルであれば、Pythonが書けなくても十分活躍できます。
むしろ、「プロンプトの工夫」や「業務に合わせた使い分け」のほうが重要になる場面も多いです。
逆に、Pythonを学んでおくメリットが大きいケースは次の通りです。
- LLMアプリ開発や、RAG・エージェントなどを自分で実装してみたい
- 生成AIエンジニアやAIエンジニア寄りの転職・キャリアチェンジを狙っている
- データ分析や機械学習と組み合わせて、高度な自動化やサービス開発をしたい
このレベルを目指すなら、Pythonはほぼ必須と言ってよいでしょう。
当サイトには Pythonの完全無料テキスト がそろっていますので、
- 「まずは独学でPythonの入門部分を触ってみる」
- 「続けられそう・面白そうと感じたら、Python寄りの生成AIスクールも選択肢に入れる」
というステップを踏んでみるのも良いと思います。
どのくらい学習時間を確保できれば、スクール受講に向いていますか?
学習時間の目安は、「スクールの難易度」と「あなたの目的」によって変わりますが、目安として次のラインを意識すると判断しやすくなります。
一般的なスクールでは、公式サイトなどで
- 週◯時間程度の学習を想定
- 全期間で合計◯◯時間程度の学習量
といった目安が公開されていることが多いです。
そのうえで、社会人の場合は、次のような感覚で考えてみてください。
- 週5〜7時間程度:
平日1時間+週末2〜3時間ペース。
→ ノーコード中心の講座や、リテラシー寄りのコースなら、十分ついていけることが多いです。 - 週8〜12時間程度:
平日1〜1.5時間+週末3〜4時間ペース。
→ Python+生成AIアプリ開発や、ポートフォリオづくりを含むコースなら、このあたりから現実的になってきます。 - 週15時間以上:
平日2時間+週末4〜5時間ペース。
→ エンジニア転職コースや、かなり密度の濃い講座でも、しっかりこなしていきやすいラインです。
ここで大事なのは、「机上の空論ではなく、実際にこのペースで3か月続けられそうか?」という現実感です。
仕事や家庭の予定をざっくりカレンダーに書き出してみて、「これなら何とか回せそうだな」と感じられるかどうかを、自分なりにチェックしてみてください。
もし、どうしても時間が取れなさそうなら、
- まずは独学や短期講座で様子を見る
- 学習時間が確保できるタイミングに合わせて、本格的なスクール受講を検討する
といった順番のほうが、無理なく続けやすいです。
まだ目的がはっきり決まっていないのですが、それでもスクールに申し込んで大丈夫?
「転職か、副業か、業務効率化か…まだハッキリ決め切れない」という状態のまま、スクールを検討している方も多いと思います。
この場合のポイントは、「目的がぼんやりしていても大丈夫なスクール」と、「目的が定まっていないと苦しくなるスクール」があるという点です。
目的がまだぼんやりしていても進めやすいのは、次のようなタイプです。
- 生成AIのリテラシーやビジネス活用を、幅広く体験できる講座
- コミュニティ型で、いろいろな人の活用例に触れられるスクール(SHIFT AI など)
- 「Pythonもノーコードも少しずつ触ってみる」ような入門的コース
こうしたスクールでは、学びながら「自分はこの分野が好きかも」「この用途にはあまりワクワクしないな」といった感覚がつかめてくるので、途中で方向性を修正しやすいのがメリットです。
一方で、目的が曖昧なままだときつくなりやすいのは、
- エンジニア転職特化で、ハードな学習量が求められるコース
- 明確なビジネス目標(◯ヶ月で◯万円など)を前提に設計されているコース
といったタイプです。
こうしたスクールは、モチベーションの軸がはっきりしていないと、途中で「自分は何のために頑張っているんだろう?」と迷いやすくなります。
もし現時点で目的がはっきりしない場合は、
- まずは本記事のマトリクスを見ながら、「一番近いタイプ」を仮決めする
- そのタイプと相性の良さそうなスクールの無料相談・説明会・体験会をいくつか受けてみる
というステップを踏むのがおすすめです。実際に話を聞いてみると、自分の中で「これがやりたい」「これは違う」といった感覚がかなりはっきりしてくるはずです。
まとめ|「技術×目的」で考えれば、生成AIスクール選びはラクになる
ここまでかなり長い記事になりました。
生成AIスクールは、どれも安い買い物ではありませんし、「この1回の選択で人生が全部決まる」と感じてプレッシャーになってしまうこともあると思います。
ただ、実際には、
- まずは独学や短い講座で試してみる
- 無料相談や説明会で、自分の状況を相談してみる
- 必要なら途中で方向転換する
といった“小さく試しながら決める”進め方も十分可能です。
もし、この記事を読み終えた今、
- 自分の目的がなんとなく言語化できた
- Python寄りかノーコード寄りかのイメージがついた
- 気になるスクールが2〜3社に絞れそう
と感じられていれば、それだけで大きな前進です。
あなたが、自分に合ったスタイルで生成AIを学び、仕事や人生にうまく活かしていけるよう、この記事が少しでもその後押しになればうれしいです。