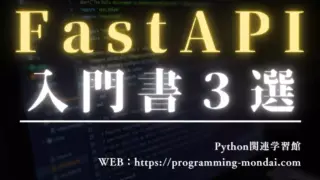【2026年最新】FastAPIとは?|Flaskとの違いと選び方解説
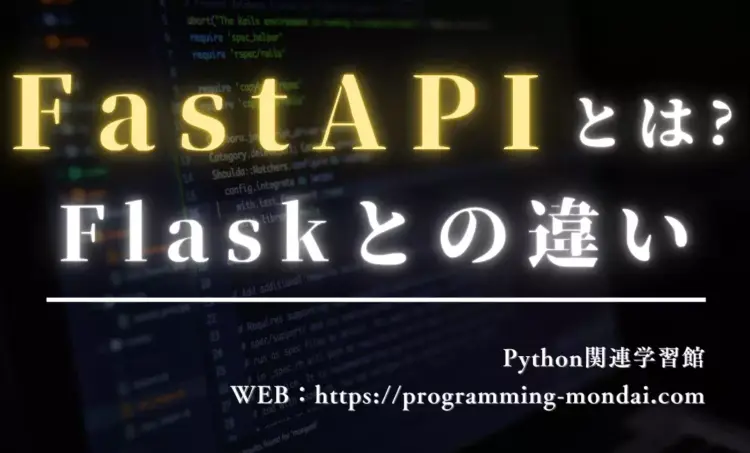
PythonでWeb開発を始めようと思ったとき、まず候補にあがるのが「Flask」と「FastAPI」ではないでしょうか。
どちらも軽量で人気のある Webフレームワーク ですが、2026年の今はFastAPIが急速に存在感を増しているのが現状です。
とはいえ、「FastAPIとはどんなフレームワーク?」「Flaskと何が違うの?」と感じる方も多いはず。
特にPythonを学び始めたばかりのエンジニアにとって、どちらを選ぶかは悩ましい問題ですよね。
この記事では、FastAPIが伸びている理由とFlaskとの違いを、2026年のトレンドを踏まえてやさしく解説します。
宗教論争のような「どっち派が正義」といった話ではなく、「どっちが自分に合うか」 を一緒に整理していきましょう。
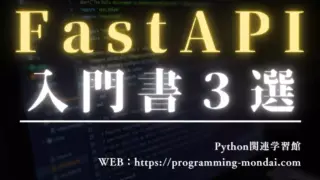

FastAPIとは|機能と特徴を解説
FastAPI(ファストエーピーアイ)は、2019年に登場した比較的新しいPython製のWebフレームワークです。
名前の通り「速さ(Fast)」が特徴ですが、実際の魅力はスピードだけではありません。
そもそもフレームワークとは何かを詳しく知りたい人は、さきに以下の記事を参照してください。

非同期処理(async/await)に対応
FastAPIはPythonの 非同期処理(asyncio)に対応しています。
これにより、大量のリクエストを同時に処理するようなAPIでも、高速に動作します。
例えばチャットアプリやリアルタイムAPIなど、同時接続が多い場面に強いのが特徴です。
型ヒントを活かした自動ドキュメント生成
FastAPIのもう一つの大きな特徴は、Pythonの 型ヒント(type hints)を積極的に活用していることです。
型を明示するだけで、Swagger UIやOpenAPI仕様に沿った自動APIドキュメントを生成できます。
これはFlaskでは標準ではできない機能で、開発の効率と品質を大きく高めてくれます。
データ検証が強力(Pydanticの採用)
FastAPIは内部的に Pydantic というライブラリを使っており、入力データの検証(validation)が非常にしっかりしています。
たとえば「整数であること」「必須項目であること」といったチェックを自動で行い、バグを防ぎやすくします。
初心者にも理解しやすい構造
コードの書き方はFlaskに似ており、直感的で学びやすいです。
以下のサンプルを見れば、そのシンプルさが伝わるでしょう。
from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()
@app.get("/")
def read_root():
return {"message": "Hello FastAPI!"}このコードを実行するだけで、http://localhost:8000 にアクセスすれば「Hello FastAPI!」というJSONが返ってきます。
さらに、http://localhost:8000/docs にアクセスすると、Swagger UIで自動生成されたドキュメントを確認できます。
Flaskとの違い は、まさにここ。
Flaskではルートを定義してもドキュメントは自動生成されませんが、FastAPIでは型とデコレーターを定義するだけで高品質なAPIが完成します。
2026年現在、需要が急速に高まっている 生成AIエンジニア。
副業にも転職にも、今から学ぶなら最もおすすめの技術ですよ↓↓


Flaskとは|いまなお人気が高い理由
FastAPIが近年急速に注目を集めている一方で、FlaskはいまなおPythonのWeb開発で最も定番のフレームワークの一つです。
リリースは2010年と歴史が長く、数多くの企業や個人プロジェクトで採用されています。
ここでは、その理由と特徴を整理してみましょう。

軽量で自由度の高い設計
Flaskの最大の特徴は、「必要最小限でできている」ことです。
つまり、フレームワーク側があまり決めすぎない設計になっており、自由度が高いのです。
Djangoのように「最初から機能が全部入っている」フルスタック型とは違い、Flaskはとてもシンプル。
基本機能はルーティングとテンプレート機能のみで、データベースや認証などは必要に応じて拡張機能(Extension)を追加していくスタイルです。
この「足りないところを自分で組み立てる」自由さが、多くの開発者に好まれています。
特に 学習目的や小規模なアプリに最適で、Pythonを使ったWeb開発の最初の一歩として理想的 です。
コードが短く、理解しやすい
Flaskのコードは非常にシンプルで、最小構成なら10行ほどで動かせます。
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def hello():
return "Hello Flask!"この短いコードで、http://localhost:5000/ にアクセスすればブラウザに「Hello Flask!」と表示されます。
FastAPIと比べると、返り値がシンプルなテキストで、型や自動ドキュメントといった機能はありません。
ですが、逆にそれが「とっつきやすさ」につながっています。
学習リソースとコミュニティが圧倒的に豊富
Flaskは10年以上の歴史があり、チュートリアル・サンプルコード・Stack Overflowの回答など、学習情報が非常に豊富です。
エラーに遭遇しても、検索すればほとんどの場合すぐに解決策が見つかります。
また、大学・専門学校・オンライン講座でもよく採用されており、PythonのWeb開発入門としては今も定番です。
Flaskの人気が続く理由まとめ
- 軽量で自由:必要な機能だけを選んで追加できる
- 学びやすい:シンプルな構造で理解しやすい
- 情報が多い:日本語記事も豊富で初心者に優しい
Flaskは、「とりあえず動かしてみたい」「自分で構成を組みたい」という開発者にとって最適な選択肢です。
FastAPIがモダンで高機能になった今でも、“軽さ”と“自由度”という魅力は失われていません。

FastAPIとFlaskの違いを比較(2026年版)
ここまでで、FastAPIとFlaskそれぞれの特徴を見てきました。
どちらもPythonでWeb開発を行ううえで非常に優れたフレームワークですが、目指している方向性や設計思想が少し異なります。
ここでは、2026年現在のトレンドも踏まえて、性能面・開発体験・学びやすさの3つの視点で比較してみましょう。
FastAPIとFlaskの違い一覧・比較表
FastAPIとFlaskを大まかに比較すると、以下のような違いがあります。
この表では、リリース年や処理方式、パフォーマンス、向いている用途など、基本的な観点から両者を俯瞰できます。
| 比較項目 | FastAPI | Flask |
|---|---|---|
| リリース年 | 2019年 | 2010年 |
| 処理方式 | 非同期(async対応) | 同期処理のみ |
| 型サポート | Pythonの型ヒントを活用(自動ドキュメント生成) | 型ヒントなし(自由だが安全性低め) |
| ドキュメント生成 | 自動(Swagger / OpenAPI対応) | 手動で対応が必要 |
| 開発スピード | 設計が整っており中〜高速 | 初期は速いが、規模拡大でやや複雑化 |
| 学習コスト | やや高い(型やasyncの理解が必要) | 低い(直感的) |
| 拡張性 | 標準でモダンAPI構築に最適化 | 拡張機能を自由に追加可能 |
| 向いているプロジェクト | API・AI・マイクロサービス | 小規模アプリ・学習用途 |
| パフォーマンス | 高速(Starletteベース) | 標準的(WSGIベース) |
処理モデルの違い:「非同期」と「同期」
2つのフレームワークの最も大きな違いの一つが、リクエスト処理の仕組み(処理モデル)です。
Flaskは、古くからある「WSGI」という仕組みを採用しています。
これは1リクエストを1スレッドで処理するスタイルで、構造がシンプルな反面、同時アクセスが多いと性能が低下しやすい特徴があります。
一方、FastAPIは次世代の「ASGI」規格 を採用しています。
ASGIは非同期(async)処理をサポートしており、複数のリクエストを同時に処理できます。
そのため、チャットアプリやリアルタイム通信、AIモデルのAPIサーバーのような高トラフィック環境でも、安定して動作します。
言い換えれば、FastAPIは「スピード」と「スケーラビリティ」を意識して設計されたモダンな基盤なのです。
型安全性と開発効率の違い
もう一つの違いは、「型情報(type hints)」を活用するかどうかです。
Flaskでは型を使う文化がなく、すべての入力値を自分でチェックする必要があります。
一方、FastAPIはPythonの型ヒントを使ってデータ検証と自動ドキュメント生成を同時に実現します。
以下のサンプルを見てください。
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
app = FastAPI()
class User(BaseModel):
name: str
age: int
@app.post("/users")
def create_user(user: User):
return {"message": f"{user.name} さんを登録しました。"}このわずかなコードで、FastAPIは次のようなことを自動で行ってくれます。
ageに文字列が入っていればエラーを返す(型チェック)- Swagger UIでAPIの仕様を自動生成
- IDEで型補完をサポートし、開発効率を向上
Flaskで同じことを行う場合、marshmallowやflask-restxなどの外部ライブラリを追加しなければなりません。
つまりFastAPIは、「型を使う開発文化」が標準で備わったフレームワークなのです。
学習・運用の違い
学習コストと運用のしやすさも、FastAPIとFlaskの重要な違いです。
Flaskはとにかくシンプルで、構成を自分で自由に作れるのが魅力ですが、自由すぎてチームごとに設計方針がバラバラになりやすいという側面があります。
FastAPIは設計がしっかりしており、コードスタイルも統一しやすいため、チーム開発や長期運用に向いています。
ただし、非同期処理や型などの知識が前提となるため、最初の一歩では少し学習コストが高めです。
そのため、最近では多くの学習者が
👉 「まずFlaskで基礎を学ぶ」
👉 「その後FastAPIでモダン開発に挑戦する」
という2段階学習の流れを取るようになっています。
まとめ:FlaskとFastAPIの違いを一言でいうと?
最後に、2つのフレームワークの違いを一言でまとめてみましょう。
以下の表は、設計思想や開発スタイルの違いを端的に示したものです。
| 要約 | Flask | FastAPI |
|---|---|---|
| コンセプト | 「自由なミニマル設計」 | 「型安全で高速なモダンAPI」 |
| 雰囲気 | 自由研究的・学習に最適 | 現場志向・チーム開発向け |
| 例えるなら | 自作キットのような楽しさ | 組み立て済みの高性能ツール |
どちらも優れた選択肢ですが、「目的に応じて選ぶ」のが2025年の正しい考え方です。
「まず動かして学びたい」ならFlask、「本格的なAPIを構築したい」ならFastAPI、というように使い分けるのがベストです。
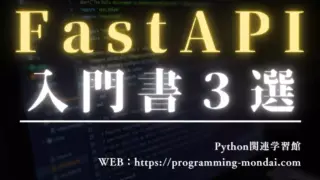
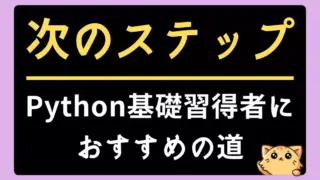
2026年のトレンド|なぜFastAPIが伸びているのか
ここ数年、PythonのWeb開発界隈では「FastAPI」という名前を聞かない日はないほど話題になっています。
2019年の登場からわずか数年で、GitHub のスター数はFlaskを超え、多くの企業が採用を進めています。
では、なぜここまでFastAPIが人気を集めているのでしょうか?
2026年のトレンドを踏まえて、その背景を見ていきましょう。
AI・機械学習分野での採用が急増
FastAPIの普及を大きく後押ししたのが、AI・機械学習(ML)プロジェクトでの利用増加です。
ChatGPTやLangChainなどの登場により、PythonでAPIを構築してAIモデルを提供するケースが急増しました。
これらのAI APIでは、
- リクエスト数が多い(非同期が必要)
- データの入出力形式が複雑(JSON構造のバリデーションが必要)
- 外部サービスとの通信が頻繁
といった要件があります。
FastAPIはこれらを標準機能だけで解決できるため、AI開発者にとって非常に相性が良いのです。
たとえば、OpenAIのAPIを呼び出してレスポンスを返すような小さなAIサーバーも、astAPIなら数十行で書けてしまいます。
この “速く作れて速く動く” 感覚が、多くのエンジニアを魅了しています。
APIファースト開発の普及
もう一つの要因は、APIファースト開発 の広がりです。
これは「まずAPIを設計し、それを中心にフロントエンドやモバイルを連携させる」という開発スタイルのこと。
モダンなWebアプリやSaaSでは、この考え方が主流になっています。
FastAPIは、このAPIファーストな開発に理想的なフレームワークです。
理由は次の通りです。
- OpenAPI仕様を自動生成(Swagger UIで確認可能)
- JSON通信に最適化されたデフォルト構造
- スキーマ定義(Pydantic)でAPI設計と検証が一体化
これらの特徴により、フロントエンド・バックエンド間のやり取りが非常にスムーズになります。
特にチーム開発では、「APIの仕様書を書かなくても自動で共有できる」ことが大きなメリットです。
型安全と自動化の流れにマッチ
2026年のPython界隈では、型安全なコードへの意識が以前より高まっています。
mypyやPyrightなどの型チェックツールが普及し、「型を書いて静的にバグを防ぐ」文化が根付きつつあります。
FastAPIはこの流れに完全にマッチしています。
Pythonの型ヒントを活用し、IDEでの補完・検証・自動ドキュメント生成がすべて連動する設計になっているため、「型を書くこと=開発の効率化」につながる仕組みが整っています。
この点は、型を使わないFlaskとは明確に異なる方向性です。
「より安全で、自動化された開発」を志向する現代の開発者にとって、FastAPIは自然な選択肢となっています。
クラウド・サーバーレスとの親和性
さらに、クラウド環境での動作のしやすさもFastAPI人気の大きな理由です。
AWS Lambda、Azure Functions、Google Cloud Runなどのサーバーレス環境では、起動が速く軽量なASGIアプリが求められます。
FastAPIはまさにその要件にピッタリ。
- 非同期I/Oでスケーラブル
- 軽量構成でデプロイが容易
- コンテナ化(Docker)に最適化
これにより、クラウドネイティブな環境でのAPI開発において、Flaskよりも圧倒的に扱いやすいフレームワークとなっています。
コミュニティとエコシステムの拡大
最後に、FastAPIは登場してからの期間が短いにも関わらず、非常に活発なコミュニティを形成しています。
GitHubでは数千人規模の貢献者がアップデートや改善提案を行っており、ドキュメントもわかりやすく翻訳が進んでいます。
さらに、Starlette(Webサーバー層)やPydantic(データ層)といった強力な基盤ライブラリに支えられている点も信頼性を高めています。
そのため、個人開発から企業システムまで、幅広い層が安心して採用できる環境が整いつつあります。
まとめ|FastAPIの人気は“時代の流れ”と合致している
FastAPIがここまで伸びた理由は、単なるブームではありません。
- AI・APIファーストの時代に最適化された設計
- 型安全・自動化という開発文化との親和性
- クラウド環境でのスケーラビリティと軽量性
つまり、「いまの時代のニーズ」に最も自然にマッチしたフレームワークなのです。
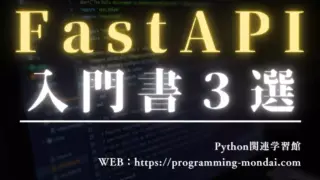
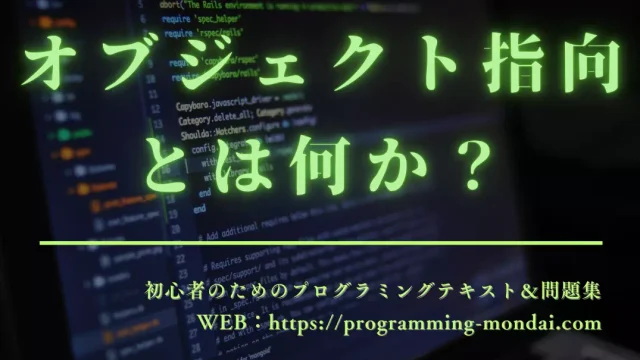
今から始めるならどっち?|選び方のポイント
ここまで読んで、「結局、自分はFlaskとFastAPIのどちらを選べばいいの?」と感じた方も多いでしょう。
実際のところ、どちらも優れたフレームワークであり、「一方が完全に上位互換」ということはありません。
大切なのは、あなたの目的と開発スタイルに合わせて選ぶことです。
ここでは、いくつかの視点から“2026年のベストな選び方”を整理してみましょう。
学習目的で使うなら「Flask」
もしあなたが Pythonを使ったWeb開発を初めて学ぶ段階であれば、Flaskから始めるのがおすすめ です。
Flaskの魅力は、とにかく「コードが短く」「動作がわかりやすい」こと。
アプリの仕組みをシンプルに理解できるため、「HTTPとは何か?」「ルーティングって何をしているのか?」といったWeb開発の基本を自然に学べます。
また、教材・記事・動画が非常に多く、日本語の情報も豊富です。
特にプログラミング学習サイトや講座では、最初のWebフレームワークとしてFlaskを使うケースが多く、学習ハードルが低いのも大きな利点です。
Flaskの学習には、是非このサイトをこのままご利用ください↓↓

APIやAI開発を目指すなら「FastAPI」
もしあなたがこれからAPI中心の開発やAIアプリの構築を目指すなら、FastAPIが断然おすすめです。
FastAPIは、Pythonの型ヒント・非同期処理・自動ドキュメントなど、現代的な開発に必要な要素を標準で備えています。
特に、機械学習モデルをAPI化して提供したり、フロントエンド(React / Vue / Next.jsなど)と通信するモダンな構成を組みたい場合には、最も相性が良い選択です。
さらに、FastAPIを一度使ってみると、「コード補完が効く」「API仕様書が自動生成される」といった “開発の気持ちよさ” を感じられるはずです。
この快適さが、FastAPI人気を支えている最大の理由でもあります。
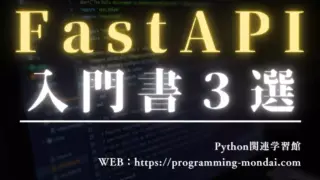
開発規模で考えるなら?
どちらを選ぶかは、アプリの規模や目的によっても変わります。
次の表を目安にしてみてください。
| 開発規模・目的 | おすすめのフレームワーク | 理由 |
|---|---|---|
| 学習・個人開発 | Flask | コードが簡潔で理解しやすい |
| 小〜中規模のAPI | FastAPI | 自動ドキュメントで効率よく開発可能 |
| チーム開発・商用プロジェクト | FastAPI | 型安全と非同期処理で保守性が高い |
| プロトタイプ・検証用アプリ | Flask | すぐ動かせて試しやすい |
| AI・データ分析API | FastAPI | 非同期処理とデータ検証が強力 |
FlaskからFastAPIへのステップアップもおすすめ
実は、FlaskとFastAPIのコード構造はよく似ています。
そのため、FlaskでWebアプリ開発の基本を学んでからFastAPIに移行するのは、非常に自然な流れです。
Flaskで「ルーティング」「リクエスト」「レスポンス」などの基礎を理解しておけば、FastAPIの学習は驚くほどスムーズになります。
しかもFastAPIはPythonの文法を活かしているので、“Pythonをより深く使いこなす” ための学びの延長線上にもなっています。
選び方の結論
- 最初の一歩なら:Flask
→ とにかくシンプルで、学習用に最適。 - 長期的にスキルを伸ばしたいなら:FastAPI
→ 現代的で、クラウド・AI時代に強い。
最終的には、どちらも「PythonでWebを作る」ことには変わりません。
大事なのは、“何を作りたいか”を明確にして選ぶことです。
Flaskで学び、FastAPIで成長する——それが2026年の最も現実的なステップアップの形でしょう。
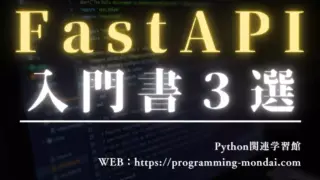

まとめ|FlaskとFastAPIのこれから
ここまで、FlaskとFastAPIの特徴や違い、そして2026年の選び方について見てきました。
どちらもPythonを代表するWebフレームワークであり、使う目的や規模によって“最適解”が変わるということが分かりましたね。
もしあなたがこれからPythonでWebアプリを作るなら、まずは「作ってみたいもの」を明確にしましょう。
学習や小さなツールならFlask、APIやAI連携をやってみたいならFastAPI。
どちらを選んでも、最終的に得られるのは「Webを自分の手で動かす楽しさ」です。
その楽しさこそが、プログラミングを続ける一番の原動力になります。
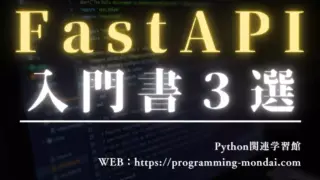

よくある質問(FAQ)
ここでは、FlaskやFastAPIについて初心者がよく抱く疑問に答えていきます。
「どっちを学ぶべき?」「何を準備すればいい?」といった悩みを一緒に解消していきましょう。
Q1. FlaskとFastAPI、最初に学ぶならどっちが簡単ですか?
A. 最初に学ぶならFlaskがおすすめです。
Flaskは非常にシンプルな構成で、最小限のコードでWebアプリを動かすことができます。
HTMLの表示やルーティングの仕組みなど、Web開発の基礎を理解するのに最適です。
FastAPIは少しモダンで高機能なぶん、型ヒント・非同期処理などの概念を理解している前提があります。
ですので、まったくの初心者ならFlaskで基礎を学び、慣れてきたらFastAPIにステップアップするのが理想的な流れです。
Q2. FastAPIを使うにはどんな知識が必要ですか?
A. FastAPIを始めるには、Pythonの基礎文法+関数+型ヒントの理解があれば大丈夫です。
FastAPIはモダンな設計のため、学び始める前に以下の知識を軽く押さえておくとスムーズです。
- Pythonの基本文法(def, class, return など)
- 型ヒント(例:
def add(a: int, b: int) -> int:のような書き方) - JSON形式のデータの扱い方
- 仮想環境(venv)や
pip installによるライブラリ管理
これらを理解していれば、FastAPIのチュートリアルをスムーズに進めることができます。
また、公式ドキュメント(日本語版もあり)が非常に丁寧なので、独学でも安心です。
Q3. Flaskで作ったアプリをFastAPIに移行できますか?
A. 完全な自動変換は難しいですが、構造が似ているので移行は比較的簡単です。
FlaskとFastAPIは、ルーティングやエンドポイントの定義方法が非常によく似ています。
そのため、1から書き直すというよりも、「一部をFastAPIスタイルに書き換える」感覚で移行できます。
例えば、FlaskのルートをFastAPIに置き換えると次のようになります。
# Flask
@app.route("/hello")
def hello():
return "Hello Flask!"
# FastAPI
@app.get("/hello")
def hello():
return {"message": "Hello FastAPI!"}このように、基本の構造はほぼ同じ。
ただし、FastAPIでは非同期関数(async def)を使ったり、Pydanticモデルでリクエストを定義したりと、少し新しい書き方が増えるため、そこは学びながら少しずつ書き換えるのがおすすめです。