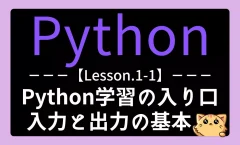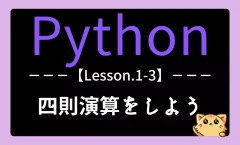【Python】レッスン1-2:変数を理解しよう
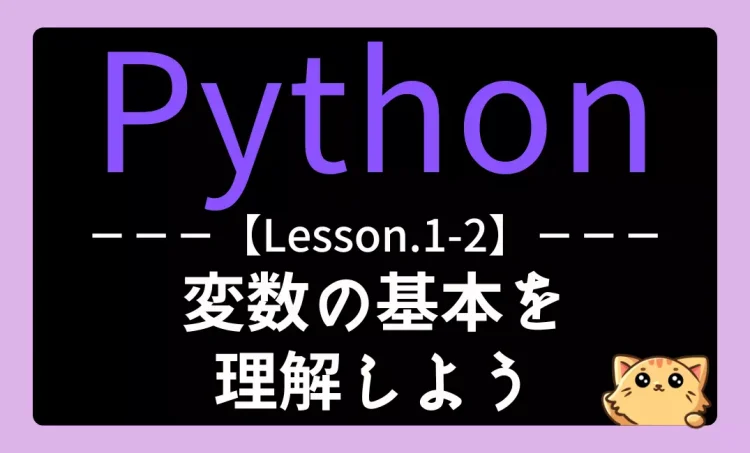
一つ前のLessonでは入力と出力の基本について学習しました。
今回は変数の基本について見ていきます。
Lesson1:基礎文法編
・Lesson1-1:Pythonの入り口|初めてコードを書いてみよう
・Lesson1-2:変数の基本を理解しよう ◁今回はココ
・Lesson1-3:四則演算をしよう
・Lesson1-4:文字列を操作しよう
・Lesson1-5:フォーマット文字列を使いこなそう
・Lesson1-6:乱数を生成しよう
・練習問題1-1:レッスン1の内容を総復習しよう
Lesson2:制御構造編
Lesson3:関数とスコープ編
Lesson4:データ構造編
Lesson5:オブジェクト指向編
次のステップ:Python基礎習得者にお勧めの道5選(実務or副業)
変数とは何か|定義と代入の基本を学ぼう
Pythonでプログラミングを始めると、必ずと言っていいほど最初に出てくるのが「変数」の概念です。
変数とは、数値や文字列などのデータを一時的に保存し、必要なときに呼び出して使える “ラベル” のようなもの。
この記事では、Pythonにおける変数の基本的な使い方や宣言方法について、初心者にもわかりやすく解説します。
これから変数を使いこなすための基礎をしっかり身につけていきましょう。続きを読んで、実際に手を動かしながら学んでみてください!

変数を宣言・代入する基本ルール
Pythonでは変数を宣言する際に特別な構文を使う必要がありません。
単に変数名を指定し、そこに「=(イコール記号)」を使って値を代入することで変数が作成されます。これがPythonの変数宣言と代入の基本的な流れです。
例えば、以下のように変数を定義し、値を代入することができます。
x = 10 #「x」という変数を作成し、「10」という数値を代入 message = "Hello" #「message」という変数を作成し、「Hello」という文字列を代入 円周率 = 3.14 #「円周率」という変数を作成し、「3.14」という数値を代入
この例では、xという変数に10を、messageという変数に”Hello”という文字列を、円周率という変数に3.14をそれぞれ代入しています。
変数名は一部の禁止キーワードを除いて、何でも好きに決めることができます。日本語でもOKです。
変数の書き方|宣言と代入のコード例
実際のプログラムの中で変数がどのように扱われるかを見てみましょう。
以下は、簡単な変数宣言と代入の例です。
# 変数の宣言と代入 a = 5 #「a」という変数を作成し、「5」という数値を代入 b = 3 #「b」という変数を作成し、「3」という数値を代入 # 変数を使って計算を行う total = a + b # 変数totalを宣言し、変数aの値と変数bの値の合計を代入 diff = a - b # 同様に差を代入 product = a * b # 同様に積を代入 quotient = a / b # 同様に商を代入 # 結果を表示 print(total) # 変数totalの中身(8)を出力 print(diff) # 出力: 2 print(product) # 出力: 15 print(quotient) # 出力: 1.666...
この例ではaとbという変数にそれぞれ値を代入し、その変数を使って加算や減算、乗算、除算を行っています。
今回はaとbに直接値を代入しましたが、input()関数を用いてユーザーに入力してもらうこともできるでしょう。
このように、変数を利用することでプログラム内でさまざまな計算やデータ処理を効率的に行うことができます。
まとめ|変数の基本がプログラムに力を与える
この記事ではPythonにおける変数の基本として、「変数の宣言」と「値の代入」の書き方を学びました。
コード例を通じて、文字列や数値を変数に保存する方法、そしてそれらを使う具体的なイメージを掴めたと思います。
この知識があることで、プログラムの中でデータを一時的に保持し、再利用する処理ができるようになります。
つまり、より柔軟で実用的なコードを書けるようになる第一歩を踏み出せたということです。
小さな積み重ねが、確かな理解と大きな成長につながります。次のステップに進む準備は、もう整っていますよ。
- サイト改善アンケート|ご意見をお聞かせください(1分で終わります)
-
本サイトでは、みなさまの学習をよりサポートできるサービスを目指しております。
そのため、みなさまの「プログラミングを学習する理由」などをアンケート形式でお伺いしています。1分だけ、ご協力いただけますと幸いです。
【Python】サイト改善アンケート
練習問題:変数を使ってみよう
この記事で学習した「変数の基本」を復習する練習問題に挑戦しましょう。
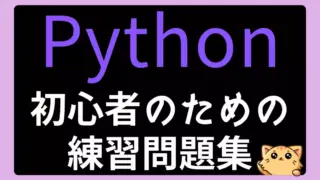

問題|変数を使った簡単な数値・文字列プログラム
変数への代入・表示と、ユーザー入力の基本を練習します。
2つの数値を変数に保持して順に表示し、その後、名前を入力してもらい、挨拶を表示するプログラムを作成してください。
以下の要件に従ってコードを完成させてください。
- 変数 x と y に、それぞれ 10 と 5 を代入する。
- print 関数で x・y を表示する。
- input 関数で名前を受け取る(プロンプトは「あなたの名前を入力してください: 」)。
- 受け取った名前で挨拶を表示する。
ただし、以下のような実行結果となるコードを書くこと。
変数xの値は: 10 変数yの値は: 5 あなたの名前を入力してください: 太郎 こんにちは、 太郎
【ヒント】難しいと感じる人だけ見よう
1からコードを組み立てることが難しい場合は、以下のヒントを開いて参考にしましょう。
- ヒント1【コードの構成を見る】
-
正解のコードは上から順に以下のような構成となっています。
1:2つの整数を変数に代入し、ラベル→値の順で画面に表示
・x と y に指定の整数を入れる。
・表示は「ラベル → 値」を x と y でそれぞれ行う。
・ラベルの文言は課題どおり(「変数xの値は:」「変数yの値は:」)にする。
・出力は1回ごとに改行されることを前提に、余計な空白や記号を入れない。2:変数yに5を代入
・入力用の関数に指定のプロンプト文を渡して、戻り値を変数に入れる。
・表示は2回呼び出し、1回目は「こんにちは、」、2回目は入力された名前をそのまま。
- ヒント2【穴埋め問題にする】
-
以下のコードをコピーし、コメントに従ってコードを完成させて下さい。
# 数値を代入する変数 x = 10 # 変数xを宣言し、10を代入 y = '''(穴埋め)''' # 変数yを宣言し、5を代入 # 変数の値を出力 print("変数xの値は:") print(x) # 変数xの値をそのまま出力 print("変数yの値は:") print(y) # 変数yの値をそのまま出力 # 文字列を代入する変数 '''ここに、input 関数でユーザー名を受け取り、変数 name に代入するコードを書く''' # 入力された名前を表示します print("こんにちは、") print('''(穴埋め)''')
このヒントを見てもまだ回答を導き出すのが難しいと感じる場合は、先に正解のコードと解説を見て内容を理解するようにしましょう。
解答例|変数を扱う練習コード紹介
例えば以下のようなプログラムが考えられます。
- 正解コード
-
# 数値を代入する変数 x = 10 # 変数xを宣言し、10を代入 y = 5 # 変数yを宣言し、5を代入 # 変数の値を出力 print("変数xの値は:") print(x) # 変数xの値をそのまま出力 print("変数yの値は:") print(y) # 変数yの値をそのまま出力 # 文字列を代入する変数 name = input("あなたの名前を入力してください: ") # ユーザーに名前の入力を促します # 入力された名前を表示します print("こんにちは、") print(name)
解答例の解説|変数を扱う練習コードの考え方
解答例の詳細解説は以下の通りです。
- 詳細解説
-
2つの整数を変数に代入し、ラベル→値の順で画面に表示
# 数値を代入する変数 x = 10 # 変数xを宣言し、10を代入 y = 5 # 変数yを宣言し、5を代入 # 変数の値を出力 print("変数xの値は:") print(x) # 変数xの値をそのまま出力 print("変数yの値は:") print(y) # 変数yの値をそのまま出力- まず、変数 x と y を用意して、それぞれに 10 と 5 を入れます。Python では代入した瞬間に変数が作られるため、事前の宣言は不要です。
- 出力は「説明文(ラベル)」と「実際の値」をセットで行います。最初に「変数xの値は:」というラベルを表示し、その次の行で x の中身を表示します。続いて y についても同じ手順で出力します。
- 出力関数は呼び出すたびに自動で改行されるため、ラベルと値は別の行になります。
- 文字列を表示するときはダブルクォーテーションで囲みます。
- 記号「=」は「等しい」という意味ではなく、右側の値を左側の変数に入れる“代入”を表します。
ユーザーから名前を入力で受け取り、2行の挨拶(「こんにちは、」→次の行に名前)を表示
# 文字列を代入する変数 name = input("あなたの名前を入力してください: ") # ユーザーに名前の入力を促します # 入力された名前を表示します print("こんにちは、") print(name)- 入力用の関数で、画面に指定のメッセージを表示してユーザーの入力を待ち、その文字列を変数に保存します。今回のプロンプト文は課題に示された日本語の文言をそのまま使います。
- 入力された名前は文字列として扱われるため、数値への変換などは不要です。
- 表示は2回に分けて行います。最初に挨拶の文(「こんにちは、」)だけを出力し、次の行でユーザーが入力した名前をそのまま出力します。
- 出力関数は呼び出すたびに自動で改行するため、挨拶と名前が別行に並びます。
- 課題の指定どおり、名前に「さん」や記号を付け足さないことがポイントです。余計な空白や句読点も付けないようにします。
変数の疑問解消|FAQと用語のまとめ
初心者がつまずきやすいポイントをFAQとしてまとめ、またよく使う専門用語をわかりやすく整理しました。
理解を深めたいときや、ふと疑問に感じたときに役立ててください。
FAQ|変数に関するよくある質問
- Q1. 変数名は日本語でも使えるの?
-
技術的には使えますが、英語で簡潔に名前を付けるのが一般的です。保守性や他者との協働のためにも英語を推奨します。
- Q2. 変数に再代入すると前の値はどうなるの?
-
再代入すると、以前の値は上書きされます。古い値は保持されないので、必要な場合は別の変数に保存しておきましょう。
- Q3. 複数の変数を一行で定義できますか?
-
はい、
a, b = 1, 2のように一行で複数の変数を定義できます。レッスン4で学習するリストなどを使うと、より柔軟な操作も可能です。
Python用語集|変数に関する用語一覧
今回の記事で出てきた用語・関数などを一覧で紹介します。
このサイトに出てくる 全てのPython用語をまとめた用語集 も活用してください。
| Python用語 | 定義・使い方の概要 | 解説記事へのリンク |
|---|---|---|
| 変数 | データを一時的に保存し、名前を付けて扱えるようにする入れ物 | 本記事 |
| データ型 | 値がどのような種類のデータであるかを示す分類。 例:整数、文字列、浮動小数点など | 本記事 Lesson1-3 |
整数型( int 型) | 整数(例:1、-5、100)を扱うデータ型 | 本記事 Lesson1-3 |
浮動小数点型( float 型) | 小数(例:3.14、-0.01)を扱うデータ型 | 本記事 Lesson1-3 |
文字列型( str 型) | テキスト(例:”Hello”)を扱うデータ型 | 本記事 Lesson1-3 |
| 算術演算子 | 四則演算を行うための記号。 例:加算( +)、減算(-)、乗算(*)、除算(/) | Lesson1-3 |
覚えたPythonでお金を稼ごう
あなたは何のためにPythonを勉強していますか?
Pythonは様々な分野で利用される、非常に万能な言語です。しかしPythonの基礎を覚えただけでは、業務や副業には直結しません。
Pythonはあくまでも基礎。それを応用する方法を考えないといけません。
2025年現在、最もお勧めなのは 生成AIエンジニア になる道。
ChatGPTなどのAIを理解し、それをPythonで動かせるエンジニアになれば、そのスキルだけで当面は安泰でしょう。

その方向へ進む場合は、経済産業省のお墨付きもある DMM 生成AI CAMP で学ぶことが最も確実で近い道です。
Pythonの基礎も含めて学習できますので、興味のある方はぜひ↓↓のレビュー記事を参考にしてください。

もしくは、生成AIが誕生するよりも以前からあり、今後も根強い需要があると思われる、汎用的なPythonエンジニアになるのもお勧めです。
Excelの自動化技術 を覚えれば、副業でコツコツ稼ぐこともできるでしょう。
2025年現在、Pythonを用いてどのようにお金を稼ぐのが効率的なのか。
是非↓↓の記事を参考にしてください。