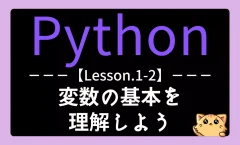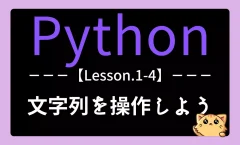【Python】レッスン1-3:データ型と算術演算子を理解しよう
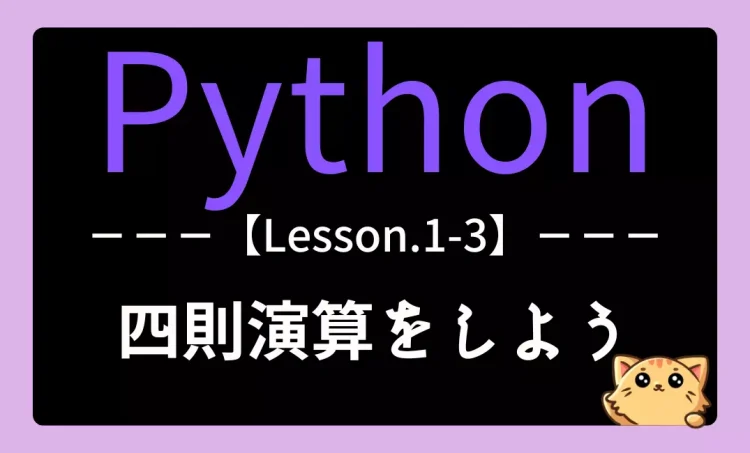
一つ前のLessonでは変数の基本について学習しました。
今回は基本データ型と算術演算子について見ていきます。
Lesson1:基礎文法編
・Lesson1-1:Pythonの入り口|初めてコードを書いてみよう
・Lesson1-2:変数の基本を理解しよう
・Lesson1-3:四則演算をしよう ◁今回はココ
・Lesson1-4:文字列を操作しよう
・Lesson1-5:フォーマット文字列を使いこなそう
・Lesson1-6:乱数を生成しよう
・練習問題1-1:レッスン1の内容を総復習しよう
Lesson2:制御構造編
Lesson3:関数とスコープ編
Lesson4:データ構造編
Lesson5:オブジェクト指向編
次のステップ:Python基礎習得者にお勧めの道5選(実務or副業)
データ型と算術演算子の基礎を学ぼう
Pythonを使ってプログラムを書く上で欠かせないのが「データ型」と「算術演算子」です。
データ型は数値や文字列といったデータの種類 を表し、算術演算子は足し算・引き算・掛け算・割り算といった計算を行うための基本的な記号 です。
これらの仕組みを理解することで、単純な計算処理だけでなく、数値データを扱うさまざまなプログラムを作れるようになります。
それでは、Pythonの基礎を支えるデータ型と算術演算子について、一緒に見ていきましょう。

基本データ型とは何か?|データの種類を理解しよう
変数にはどのような種類のデータを保存するかを決める「型」があり、代入された値によって自動的に決まります。
例えば数値を代入すればその変数は 整数型(int)または 浮動小数点型(float)となり、文字列を代入すればその変数は 文字列型(str)になります。
型の宣言が必要なく自動的に決まる点がPythonの大きな特徴と言えます。
x = 10 # 「x」は整数型(int)の変数 円周率 = 3.14 # 「円周率」は浮動小数点型(float)の変数 message = "Hello" # 「message」は文字列型(str)の変数 x = 20 # 整数型の変数xに異なる整数を再代入(値の更新) x = "Python" # エラー(整数型の変数に文字列は代入できない)
Pythonではこようにデータ型を明示的に宣言する必要はなく、値を代入するとその型が自動的に決定されます。
この場合、整数型の変数xにあとで何か別の値を代入しようとしても、xは整数以外のデータは受け付けることができません。
ちなみにJava言語の場合だと、整数を宣言するなら「int a = 5」、文字列を宣言するなら「string message = Hello, Java!」のように、毎回型を記載する必要があります。
- コラム:浮動小数点とは?
-
float型とは?浮動小数点数の仕組みと注意点
Pythonで小数を扱うときに使う
float(浮動小数点数)は、コンピュータが小数を表現するための方法です。ただし、すべての小数が正確に表せるわけではありません。
例えば、
0.1 + 0.2を計算すると0.3ではなく0.30000000000000004のような結果になることがあります。これは、
0.1や0.2が2進数では無限に続く小数になり、丸め誤差が生じるためです。この現象はPythonに限らず、ほぼすべての言語で共通です。正確な小数計算が必要な場合は、Lesson5で学習する
decimalモジュール を使うのが安全です。浮動小数点数は便利ですが、誤差が出ることを理解して使うことが大切です。
算術演算子とは何か?|基本的な使い方とコード例
算術演算子 は数値の計算を行うために使用される演算子です。
よく使われる算術演算子一覧
Pythonでは基本的な算術演算子として次のようなものが提供されています。
+: 加算(例:a + b)-: 減算(例:a - b)*: 乗算(例:a * b)/: 除算(例:a / b)//: 整数除算(例:a // b、小数点以下を切り捨てた結果を返します)%: 剰余(例:a % b、余りを返します)**: べき乗(例:a ** b、aのb乗を返します)
これらの演算子を使って、数値同士のさまざまな計算を行うことができます。
算術演算子の使用コード例
次に、算術演算子を使って基本的な計算を行う例を見てみましょう。
# 2つの数値の定義 a = 10 b = 3 # 加算 sum = a + b # 変数sumを宣言し、a+bの結果を代入 print(sum) # 変数sumの中身を出力。13と出力される # 減算 diff = a - b print(diff) #7と出力される # 乗算 prod = a * b print(prod) #30と出力される # 除算 quot = a / b print(quot) #3.333...と出力される # 整数除算 int_quot = a // b print(int_quot) #3と出力される # 剰余 mod = a % b print(mod) #1と出力される # べき乗 power = a ** b print(power) #1000と出力される
このコードでは2つの数値aとbを使って、加算、減算、乗算、除算、整数除算、剰余、べき乗の結果をそれぞれ出力しています。
これらの算術演算子を使うことで、Pythonでは簡単に計算が行えます。
まとめ|データ型と算術演算子で学んだ基礎の整理
今回学習した内容では、Pythonにおける基本的なデータ型の種類と、数値計算を行う際に用いる算術演算子の仕組みと使い方を確認しました。
整数や浮動小数点数といったデータ型を理解し、演算子を組み合わせて計算処理を記述できるようになったことで、今後のプログラミング学習に欠かせない基盤が整ったといえます。
この段階で身につけた知識は、単なる数値計算だけにとどまらず、より複雑なプログラムを組み立てる際にも必ず役立ちます。
基礎をしっかりと押さえたことを自信につなげ、次の学習ステップにも前向きに取り組んでいきましょう。
- サイト改善アンケート|ご意見をお聞かせください(1分で終わります)
-
本サイトでは、みなさまの学習をよりサポートできるサービスを目指しております。
そのため、みなさまの「プログラミングを学習する理由」などをアンケート形式でお伺いしています。1分だけ、ご協力いただけますと幸いです。
【Python】サイト改善アンケート
練習問題:基本データ型と算術演算子を使ってみよう
この記事で学習した「基本データ型と算術演算子」を復習する練習問題に挑戦しましょう。
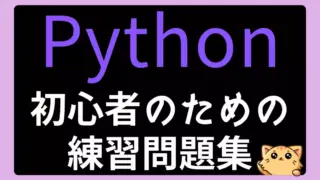

ユーザーから入力された2つの数値を使い、算術演算子を利用して計算を行うプログラムを作成してください。
ただし、計算結果のコードは以下のように指定します。
加算結果 = a + b # 変数「加算結果」を宣言し、a+bの結果を代入
print(f"加算結果: {a} + {b} = {加算結果}")これは フォーマット文字列 というまだ学習していない書き方ですが、今回はこれをマネしてその他の計算コードを書いてください。
問題|ユーザー入力を使った算術演算プログラムを作ろう
以下の要件に従ってコードを完成させてください。
- ユーザーに2つの数値を入力させ、整数として受け取ること
- 7種類の算術演算(加算・減算・乗算・除算・整数除算・剰余・べき乗)を行うこと
- 各計算結果を画面に表示すること
ただし、以下のような実行結果となるコードを書くこと。
1つ目の数値を入力してください: 10 2つ目の数値を入力してください: 3 加算結果: 10 + 3 = 13 減算結果: 10 - 3 = 7 乗算結果: 10 * 3 = 30 除算結果: 10 / 3 = 3.333... 整数除算結果: 10 // 3 = 3 剰余結果: 10 % 3 = 1 べき乗結果: 10 ** 3 = 1000
【ヒント】難しいと感じる人だけ見よう
1からコードを組み立てることが難しい場合は、以下のヒントを開いて参考にしましょう。
- ヒント1【コードの構成を見る】
-
正解のコードは上から順に以下のような構成となっています。
1.数値入力
1-1. 1つ目の数値をユーザーに入力させる
1-2. 2つ目の数値をユーザーに入力させる
2.加算処理
2-1. 入力された数値の加算を行う
2-2. 加算結果を出力する
3.減算処理
3-1. 入力された数値の減算を行う
3-2. 減算結果を出力する
4.乗算処理
4-1. 入力された数値の乗算を行う
4-2. 乗算結果を出力する
5.除算処理
5-1. 入力された数値の除算を行う
5-2. 除算結果を出力する
6.整数除算処理
6-1. 入力された数値の整数除算を行う
6-2. 整数除算結果を出力する
7.剰余処理
7-1. 入力された数値の剰余を計算する
7-2. 剰余結果を出力する
8.べき乗処理
8-1. 入力された数値のべき乗を計算する
8-2. べき乗結果を出力する
- ヒント2【穴埋め問題にする】
-
以下のコードをコピーし、コメントに従ってコードを完成させて下さい。
# ユーザーに2つの数値を入力してもらいます。 a = int(input("1つ目の数値を入力してください: ")) b = int(input("2つ目の数値を入力してください: ")) # 算術演算子を使った計算 """【穴埋め問題1】 ここに2つの数値の加算を行い、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"加算結果: {a} + {b} = {加算結果}") """【穴埋め問題2】 ここに2つの数値の減算を行い、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"減算結果: {a} - {b} = {減算結果}") """【穴埋め問題3】 ここに2つの数値の乗算を行い、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"乗算結果: {a} * {b} = {乗算結果}") """【穴埋め問題4】 ここに2つの数値の除算を行い、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"除算結果: {a} / {b} = {除算結果}") """【穴埋め問題5】 ここに2つの数値の整数除算を行い、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"整数除算結果: {a} // {b} = {整数除算結果}") """【穴埋め問題6】 ここに2つの数値の剰余を計算し、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"剰余結果: {a} % {b} = {剰余結果}") """【穴埋め問題7】 ここに2つの数値のべき乗を計算し、その結果を変数に代入するコードを書いてください。 """ print(f"べき乗結果: {a} ** {b} = {べき乗結果}")
このヒントを見てもまだ回答を導き出すのが難しいと感じる場合は、先に正解のコードと解説を見て内容を理解するようにしましょう。
解答例|算術演算プログラムのコード
例えば以下のようなプログラムが考えられます。
- 正解コード
-
# ユーザーに2つの数値を入力してもらいます。 a = int(input("1つ目の数値を入力してください: ")) b = int(input("2つ目の数値を入力してください: ")) # 算術演算子を使った計算 # 加算 加算結果 = a + b print(f"加算結果: {a} + {b} = {加算結果}") # 減算 減算結果 = a - b print(f"減算結果: {a} - {b} = {減算結果}") # 乗算 乗算結果 = a * b print(f"乗算結果: {a} * {b} = {乗算結果}") # 除算 除算結果 = a / b print(f"除算結果: {a} / {b} = {除算結果}") # 整数除算 整数除算結果 = a // b print(f"整数除算結果: {a} // {b} = {整数除算結果}") # 剰余(余り) 剰余結果 = a % b print(f"剰余結果: {a} % {b} = {剰余結果}") # べき乗 べき乗結果 = a ** b print(f"べき乗結果: {a} ** {b} = {べき乗結果}")
基本データ型と算術演算子の疑問解消|FAQと用語のまとめ
初心者がつまずきやすいポイントをFAQとしてまとめ、またよく使う専門用語をわかりやすく整理しました。
理解を深めたいときや、ふと疑問に感じたときに役立ててください。
FAQ|基本データ型と算術演算子に関するよくある質問
- Q1.
+演算子は数値と文字列どちらにも使える? -
はい、ただし型が異なる場合にはエラーになります。例えば
1 + "1"はエラーになるため、型をそろえる必要があります。
- Q2. 浮動小数点数の計算で誤差が出るのはなぜ?
-
コンピュータの内部処理では、小数を正確に表現できないことがあり、これが誤差の原因です。精度が必要な場合は
decimalモジュールを使いましょう。
- Q3.
//や%の演算子はどう使う? -
//は整数の商を、%は余りを求める演算子です。割り算の結果が整数や余りとして必要な場面で使います。
Python用語集|基本データ型と算術演算子に関する用語一覧
今回の記事で出てきた用語・関数などを一覧で紹介します。
このサイトに出てくる 全てのPython用語をまとめた用語集 も活用してください。
| Python用語 | 定義・使い方の概要 | 解説記事へのリンク |
|---|---|---|
| 変数 | 値に名前を付けてプログラム内で再利用できるようにする仕組み | Lesson1-2 |
| 基本データ型 | プログラム言語において最も基本的に使われるデータの種類(数値、文字列など) | 本記事 |
整数型(int 型) | 小数点を含まない数値を扱うデータ型で、正負の整数の演算に利用される | 本記事 |
浮動小数点数型(float 型) | 実数を表すために使われるデータ型で、数値の小数部分を扱える | 本記事 |
文字列型(str 型) | 文字や記号の並びをデータとして扱う型。ユーザーの入力やメッセージ表示に使用される | 本記事 |
type() 関数 | 渡された値のデータ型を調べて、その型オブジェクトを返す標準関数 | 本記事 |
| 浮動小数点 | 小数点を含む実数のこと。計算誤差が生じることがあるため注意が必要 | 本記事 |
覚えたPythonでお金を稼ごう
あなたは何のためにPythonを勉強していますか?
Pythonは様々な分野で利用される、非常に万能な言語です。しかしPythonの基礎を覚えただけでは、業務や副業には直結しません。
Pythonはあくまでも基礎。それを応用する方法を考えないといけません。
2025年現在、最もお勧めなのは 生成AIエンジニア になる道。
ChatGPTなどのAIを理解し、それをPythonで動かせるエンジニアになれば、そのスキルだけで当面は安泰でしょう。

その方向へ進む場合は、経済産業省のお墨付きもある DMM 生成AI CAMP で学ぶことが最も確実で近い道です。
Pythonの基礎も含めて学習できますので、興味のある方はぜひ↓↓のレビュー記事を参考にしてください。

もしくは、生成AIが誕生するよりも以前からあり、今後も根強い需要があると思われる、汎用的なPythonエンジニアになるのもお勧めです。
Excelの自動化技術 を覚えれば、副業でコツコツ稼ぐこともできるでしょう。
2025年現在、Pythonを用いてどのようにお金を稼ぐのが効率的なのか。
是非↓↓の記事を参考にしてください。